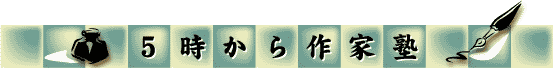第3章 何はなくとも今のあなたが
|
|
――深刻な不景気編 '96〜
|
8.フロアーの明かりはずっと消えない
ファクシミリ事業部が市場から撤退する一年前――桐畑が多摩工場から本社に異動した直後のことである。
本社、第四会議室には、ダンボール箱が積み上げられていた。社会活動貢献部に配属となった桐畑は背丈ほどもある箱の山を眺めている。箱の中身は外国コイン。前任者が従業員に呼びかけ集めたものだ。出張や旅行で海外に行くと、使い切れなかった外国コインが手元に残ることがよくある。「お金を捨てるのもなんだし……」とはいえ、日本では使えない。
三年前から社会活動貢献部で働いている郡司は、桐畑にレクチャーを始める。
「我々はこれらの通貨を日本ユニコス協会に送って、世界中の子どもたちの健やかな発達のために役立ててもらう」
企業の社会的責任、社会の一員としての活動の重要性、利益還元。
「そして、最も重要なのは、心構えで……」
「で、このダンボールどうするんですか?」
桐畑は言葉少ない説明でも、正確に状況を掴むことに長けている。配属以来、くどくどと同じ話を続ける郡司に痺れを切らし、説明を遮ったのだ。
「現在世界中には、戦争や災害、あらゆる形態の暴力、搾取の犠牲となっている子どもたちがいるわけで……」
「わかりました。それで日本ユニコス協会への送付方法はどうなっているのでしょうか」
「えーと、それは……。桐畑さんの前任に大石さんという子がいて、細かいことは任せていたから、末端の作業方法まではちょっと……」
積み上げられたダンボールは、大石が従業員に募集をかけて集めたものである。大石は退職したが、それから半年、郡司はひとつも仕事を進めていない。企画書を書くこととプレゼンテーション能力だけは秀でているタイプ。どこの会社にもいるものである。
「我々は、全社的に協力体制を整えて、推進チームを作ってやっていくつもりだったんだが、協力してくれる人が集まらなくて。うちの会社も、一人ひとりの従業員レベルとなると、その辺の認識がまだ薄いようでね」
「認識はどうでもいいことです。まずは、この仕事を進めましょう」
郡司は「わかったよ」と言い、桐畑を睨むようにして会議室を出て行った。桐畑はダンボールのテープをはがし中を覗く。ビニール袋に詰められたコインは国も金種もさまざま混ざっていた。
「桐畑さん、私は、先ほど日本ユニコスに電話したんだけど、担当者が席を外して連絡がつかなかったんだ。なんだか先方も忙しいみたいで……。私も別件を片付けなくてはいけなくて。忙しんだよなぁ」
郡司はそう言うと、机から一枚の紙を出して書き始めた。『交通費請求伝票』。経理課に提出する伝票書きが彼の言う『別件』である。桐畑はため息をつき、郡司に自分の意見を伝え、日本ユニコス協会の電話番号をダイヤルする。送付方法、運送費用負担、日程、諸々のことを擦り合わせ、受話器を置いた。
数日後、桐畑は周りの協力を得て必要な人員を集め、集まった人たちに役割りを振り分け、仕事を片付けた。
*
「どうして桐畑さんは、ああなったんですか?」
みどりの質問に桜井はためらいを見せたが、紅茶を注文したあと話し始めた。
「日本ユニコスの仕事を片付けたまでは良かったのよ」
桜井は、声を潜めみどりに言った。
「桐畑さんの行動力はピカイチ。社会活動貢献部でも一目置かれたわけ。『さすがT大卒』ってな感じで。桐畑さんは、『ただコインを送っただけなのになんで褒められるんだろ?』くらいの気持でいたんだけど、郡司さんは面白くなかったみたい。妬まれちゃったらしいのよ。郡司さんのほうが勤続年数も長いし。結局、桐畑さんは部内で浮いた存在になってしまったの。『T大卒って、そんなに偉いわけ?』なんて、よく知りもしない人に面と向かって言われたこともあったらしいわ」
「なんて、ひどいことを……」
みどりは眉をしかめた。
「桐畑さんは、自分のこと偉いなんて思ってないのにね。『上には上がいる』っていうこともちゃんと知ってるし。自分の実力にあぐらをかかない、そんな桐畑さんを私は尊敬していたわ。なのに……」
「私、桐畑さんがそんな辛い目にあったなんて、知りませんでした」
「そのことがあってから随分経つけど、今も、芝通主催のコンサートチケットを配布するとか、そんなことしか仕事がないみたい。桐畑さんが提案することは、みんなで潰しにかかるし、桐畑さんが何かしようとすると、妨げる人がいるらしいわ。『隙のない、完璧主義で、厭味な奴』なんて、陰口もたたかれてるみたいだし。運が悪かったのよ。同じ本社でも、私の周りなんて、そんなひどいことする人いないもん。仕事はハードだけどね」
みどりは今すぐ桐畑のもとに走って、何も言わず抱きしめてあげたい、と思った。
「桐畑さんは奥さんもいるし、小林さんが慰めなくても大丈夫よ。余計なことはおよしなさい。間違っても昔みたいに『私とセックスしませんか?』なんて言っちゃダメよ」
桜井はそう言って笑った。
「大丈夫ですよ。正直に言っちゃうと、入社した頃の私は桐畑さんに惹かれてたけど、桐畑さんが結婚したとき、その気持ちを小さく畳んで心の奥に埋めちゃったんです。今は、ほかに好きな人もいるし……」
「ああ、大久保君のことね」
「どーして、知ってるんですかっ?! まあ、いっか」
「ところで今、彼はどうしてるの?」
「川崎の研究所に異動して、活躍してますよ。昇進もトントン拍子です」
「そう。良かったじゃない。好きな人が成功するのって、嬉しいでしょ?」
「そうですけど、大久保君とは別に、私、今の桐畑さんが気になっちゃって……。『好き』とは別の感情ですよ。『同情』とも違う。わかります?」
「わかるような、わからないような……。桐畑さんが厳しい境遇の中にいるから、小林さんは気になってるんでしょ? そんな気がするわ」
二人はしばらく桐畑のことを話題にし、店を後にした。
みどりは部屋に戻った後も、桐畑のことが頭から離れなかった。直感の鋭い桐畑は、自分が周囲から嫌われていることを知っているのだ。できれば、そんな自分じゃなく、多摩工場にいた時みたいに、人から認められた存在でいたい――誰だってそう思うだろう。
<桐畑さん、今頃なにしているんだろ? 自殺なんか考えてないよね>
翌日もう一度、みどりは本社に向かう。きのうと同じように桐畑は封筒に糊付けをしていた。みどりは声をかけずに帰ろうか迷っていると、桐畑と視線が合った。無表情だった桐畑が複雑な顔を見せ、立ち上がる。二人は、本社ビルの中にある喫茶店に移った。
「昔、小林さんは甘いものが好きでしたけど、今でもそうですか? ここのチョコレートケーキ、美味しいんですよ」
桐畑はコーヒーと一緒にみどりのケーキも注文する。昔の桐畑なら、人の好みなんて気にもしなかった。みどりは桐畑の顔を見つめる。桐畑はテーブルに視線を落とし、「今の私は最悪の境遇ですよ」と呟いた。桐畑は自分の弱みは絶対見せない男だったはず。みどりはあっけに取られ、次の言葉まで間が空いた。
「私は桐畑さんが悪いんじゃないと思います。妬みですよ。だから、気にしないほうがいいですよ」
「ありがとう。……そうかもしれませんね。自分の能力に自信が持てない人は、成功を収め人から認められた人間を妬んだりします。それから、自分にないものを持っている人を潰そうとする人もいます。そのことに早く気づいていれば、もう少し周りとうまくやれたかもしれません」
みどりは頷き、チョコレートケーキを口に運ぶ。
「私は卒業した大学がT大だったということもあり、芝通では恵まれた環境の中で過ごしてきました。まさか自分がこんな冷や飯を喰わされることになろうとは……。集団で人から無視され、蔑まれるようなことも初めて経験しました。でも彼らの辛い態度は、きっと私に対するメッセージなんだと思うのです。彼らのおかげで、私は自分の高慢さに気づかされました」
「そうだったんですか……。でも、その郡司とかいう奴、むかつきません? 私、桐畑さんに代わって、殴って来てやりますよ」
桐畑は微笑を浮かべる。
「そんなことをしても、何にもなりませんよ。私も何年か前までは、郡司さんを憎んでいました。眠れない夜もあったくらいです。でも、誰だって欠点はあります。嫉妬やずるさや醜いものを抱えながら生きています。私も同じです。そう思うと、彼を責める気にはなれなくなったのです。そうは言っても、いつになったら出口が見つかるんだろうと、絶望的になった時期もありましたよ。でも今は、そういったものから開放されたのです」
「じゃあ、もう諦めてしまっているんですか?」
「諦めとは、すこしだけ違います。私が思うに、冷や飯は工夫して食べなきゃいけないのです。冷や飯を喰うことに慣れてしまったら、私はそれまでです。だから、この経験は次に成功するためのステップ。次の段階で必要なものを身につけるためにこの厳しい経験をしている。そう思っているのです」
「よかった。安心しました。必ず、チャンスは来ますよね。桐畑さんならしっかり掴めますよ。いつでも私は桐畑さんを応援していますから。……まあ、桐畑さんは迷惑かもしれませんけど」
みどりが笑うと、桐畑はその日初めての笑顔を見せた。
「さあ、私はそろそろ席に戻って仕事の続きをします」
桐畑は、そう言うと、伝票を持って立ち上がった。
|