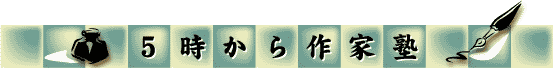第3章 何はなくとも今のあなたが
|
|
――深刻な不景気編 '96〜
|
7.本社栄転の悲劇
『事業所違えば別会社』という言葉がある。同じ芝通であるにも関わらず、事業所によって体質は異なる。2003年、芝通の従業員数は約四万人、研究所・工場は国内だけでも十箇所以上あるのだから、当然のことかもしれない。
*
芝通に南敏和というエンジニアがいる。1985年に入社し、多摩工場内の研究所に配属、ファクシミリの画像処理技術の開発に携わっていた。当時の南は、実験室で作業帽(キャップ)のつばを後ろに向け、ハンダゴテを握り「あーしてみよう、こーしてみよう」と頭の中でひらめいたことを基板の上に実現していた。新しいことに興味を持ち、追求していく性格が研究所の体質に合っていたのだろう。
順当に課長に昇格し、部下二十数名を抱え、窓の近くの席に机を構えていた南であるが、勤続15年で本社に異動となった。
「本社に移ったときは、本当にびっくりしましたよ。なにがって、まず席ですよ。入り口付近なんです。本社は管理職が多いんです。僕の周りもそうだから、仕方ないことなんですけど。新人の頃を思い出しましたね。電話で『はい、芝通でございます』って言うのも、最初は舌を噛みそうになりました」
2003年、そういう南も本社に溶け込み、携帯電話の商品企画部で活躍している。前年は携帯電話の海外展開のためヨーロッパと日本を往復した。多摩工場にいた頃と変らないことといえば、ハードな毎日を送っていることである。
*
お話は遡り90年代半ば――。
鶴見行きの京浜東北線は空いていた。会社帰りの小林みどりは空席に腰をおろし、中吊り広告に目を移す。コンビニに立ち寄ろう、などとぼんやり考えていると、一人の男性の背中が視界に入る。つり革に体重をかけるようにつかまる姿はやや内股。みどりは席を立ち顔を覗く。
「やっぱりそうだ。お久しぶりです」
声をかけた相手は、みどりがファクシミリ機械設計課で働いていたときの先輩、桜井である。みどりは配属されたばかりの頃、桜井の同性愛者的な話し方に違和感を感じていたが、やがて慣れ、困ったことがあると相談するほどの信頼を置いていた。
「小林さんじゃない! 懐かしいわ。今どうしているの?」
相変わらずオネエ言葉の桜井。
「私は芝通に復職したあと、プリンター事業部に配属となったんですけど、去年事業移管があって、今は芝通グループの関係会社で働いています。転籍が影響したのか、まだ主任にもなれないんですよ」
「私、転籍しても課長になった人、知ってるわよ。それはそうと、彼氏は?」
「相変わらずいませ〜ん」
「そう。あんた顔も性格もブスだからね。かわいそ。……せっかくだから、お茶でもしない?」
二人は次の駅で降りた。
「私はね、今は本社にいるの。悩みはね、本社でこの喋り方だと、みんながヒクってことかな……」
「本社じゃなくても、ヒクと思いますよ」
「そうかしら。だって、多摩工場の技術部門は本社に比べて年齢層が若かったでしょ。今から思うと、いい意味で言葉や態度は自由だったのよね」
私立理科系出身の桜井は、当時、正しい敬語の知識もなかったが、仕事で困ることはなかった。だいたい、上司である桐畑や課長の日野の興味は製品開発のことだけ。無作法な態度で部下がたてついても、その意見が製品にプラスになるのなら、なんとも思わないのである。
「本社に移ってから、ジンマシンができちゃって。使い慣れない男性的な言葉を使うことがストレスだったみたい」
「そうだったんですか? でも今は治ったみたいですね」
「インターネットのおかげよ。ハマってるの。ハンドルネームは『さくら』。ネット上に出没しているからよろしくね」
「もしかしてネカマ(ネットおかま)してるんですか? オネエ言葉で書き込みなんかしちゃって。相手は女だと思ってメールとか送ってくるんでしょ? 私、聞いたことありますよ」
「そうだけど、悪質なことはしてないわよ。相手を騙していることには、ちょっとだけ心が痛むけど。ジェンダーフリーってとこかな……」
「かなり意味がねじ曲げられているような……」
みどりは「やれやれ」と呟き、コーヒーを飲み込む。
「そういえば、桐畑さんも本社ですよね?」
桐畑はファクシミリ事業部が市場から撤退する前、本社に異動したのだ。
「桐畑さんは、私たちみたいに出向せずにすんだんですよね。理工系最難関の大学に合格するくらいだもの。実力はもちろん、運も強いんだな、って思いましたよ」
桐畑は本社の『社会貢献活動部』にいる。
「桐畑さんは、どんどん上に登っていく人。きっとキャリアアップのための経験なんですよね。今頃は事業部長なんかになってたりして……。懐かしいな、桐畑さんに会いたくなっちゃった」
翌日、みどりは本社を訪ねた。桐畑は、他の従業員から離れた席に腰掛け、チケットを封筒に詰め、糊付けをしていた。芝通が主催しているクラシックコンサートの事務局を社会貢献活動部が担当している。
<景気が悪いから、偉くなってもこういう仕事までしなくちゃならないのね>
背中を向けて座っている桐畑は、みどりの記憶よりも白髪が増えていた。みどりは桐畑に挨拶をしようと近寄ったとき、ひとりの男性が桐畑の席のうしろを通り、蔑むような視線を投げかけた。
「T大卒の人間がやることじゃないよな」
桐畑に聞こえるようにはっきりと言葉も投げる。
みどりは、桐畑に声をかけそびれ、突っ立ったままでいると、別の年配の男性がDMの束を抱え桐畑に近づく。
「桐畑さん、書類の封筒詰めと、宛先のシール貼り、お願いします。明日までね。最近は不景気でアルバイトを雇えないから、桐畑さんみたいに、こういう仕事を専門にしてくれる人がいると助かるんだよ」
明らかにイヤミだとわかる微笑を浮かべ、桐畑の机の上に置く。一千通はありそうだ。桐畑は動じもせず糊付けを続ける。
理工系最難関の大学を卒業し、何ひとつ躓くこともなかった桐畑。将来は、社長は無理だとしても、役員にはなるのではないかと、みどりは思っていた。それが、今は本社で学生アルバイトが担当するような仕事しかしていないのだ。
<どうしてこんなことになったのだろう>
みどりは、どうしても知りたくなる。昔のみどりだったら、桐畑のところへ駆け寄って訊いただろう。しかし、それは桐畑にとって酷なこと。そっとしておくべきだ、とみどりは思い、桐畑には挨拶もせず、桜井のいるフロアーに立ち寄った。
|