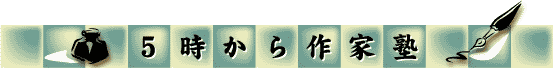第3章 何はなくとも今のあなたが
|
|
――深刻な不景気編 '96〜
|
6.希望退職制度と社会福祉士
プールでは、子どもたちがビート版に両手をつけて、ばたあしで泳いでいる。コーチの笛の合図に合わせて一人ずつ、次々と前へ進む。ガラス越しの観覧席で眺めている磯子には、気合いの入ったコーチの姿は目に入るが、声は聞こえない。
「パパ、アイス食べてから帰ろう」
一時間のレッスンが終わり、出てきた亮太の髪は、まだ乾いていない。
「来週からは、ママが連れてくるからね」
「ぼくは、パパとスイミングスクールに来たいな」
「そうも言ってられないんだよ。パパは働かなくちゃいけないんだ。そうじゃないと、ここのレッスン代だって払えなくなる」
亮太は首を傾げ、磯子を見上げた。
*
1990年にバブル景気が崩壊した後、芝通は、採用抑制による人員削減、残業規制・外部発注制限などによる費用削減、部署の統廃合によるリストラ(組織構造変革)、その他諸々……を施してきたが、業績はおもわしくなかった。
2000年の秋、子会社に行くことを拒んだ磯子は、基板製造部に配属となり、製造現場で単純作業に就く。雑談相手もいない、磯子宛には電話すらかかってこない職場である。昔のように、女の子に声をかけて、楽しく過ごす気にもなれない。気力が損なわれ、萎えてしまったのだ。
半年が過ぎ、磯子に一通の知らせが届いた。『希望退職制度』。定年前の社員に、退職金を規定より加算するなどの措置を示して、退職者を募る、といった説明が書いてあった。
<要するに、多めにお金をあげるから辞めてくれないか、ということだな>
磯子は、机の上にある定規をへし折る。べつに、磯子個人に「辞めろ」と言っているのではない。しかし、磯子は自分に向けられた通知のような気がした。
その週末夜遅く、寝室で磯子はりさ子に説得を試みた。
「よくよく計算してごらん。このまま芝通にいるより、退職金を多くもらって、失業保険をもらって、転職するほうがずっと得なんだよ!」
「でも……」
「子会社に行くように命令が下ったとき、芝通に残れるように交渉しろって言ったのはりさ子なんだよ。君の言うことを聞いたばっかりに、僕はきつい肉体労働に就くことになってしまったんだ。こんなことになるなら、会社の命令に従っとけばよかったんだよ」
同じ会話を繰り返す。そのうち、磯子は声を荒げ、りさ子は涙を流す。電話が鳴っている。
「本当は、お金の損得なんて、二の次なんでしょ?」
磯子は黙って、うつむく。受話器はリビングと書斎に置いてある。ふたりとも、受話器を取りに行く気配すら見せない。そうしているうちに、ベルは鳴り止む。りさ子は軽く溜息をついたあと、涙を拭い顔を上げた。
「もう、なにも言わない。私はあなたのことを応援するから」
りさ子は無理に笑顔を作った。
「それにしても、芝通もバカよね。あなたみたいな優秀な人材を手放そうとしているんだもん。私が社長だったら、もっともっと、むずかしい仕事をあなたにさせて、会社の業績をあげるわ」
磯子はうつむいたまま、「ありがとう」と呟いた。
磯子は一年間、社会福祉士養成施設に通い、資格を取ったのち、民間の福祉専門の会社に就職した。給料は、芝通にいたときと比べると、だいぶ少ない。それでも磯子は新しい職場が気に入っていた。
*
その日磯子は、午前と午後にそれぞれ一軒ずつ高齢者宅を訪問する予定になっていた。カウセリングや、家族に対するアドバイスが磯子の仕事である。午前中の家は、羽田の近くにある。「クニちゃん」の愛称で呼ばれている八十一歳、独り暮らし。家族はいるが、遠く離れて暮らしている。
「母が生きていることを確認してくれたらいいんです。死んだまま放ったらかしにされて、死体がドロドロに腐って、うじ虫がわく、そういったことだけは避けたいのです」
息子が訪問料を支払っている。
磯子が訪ねると、クニちゃんはお茶を淹れる。普段の生活は、自立していて、介護の必要はない。クニちゃんは椅子に座り、磯子にお茶を勧める。
「このあいだね、友だちと帝国ホテルで食事をしたの。美味しかったから、磯子さんも行ってみなさいよ」
クニちゃんの『このあいだ』は、十年以上前のことだったりする。話し相手になることも、磯子の大切な仕事のひとつ。磯子は高齢者の話を聞くのが好きだった。磯子は、「そうするよ」と答えた。クニちゃんはここ数年、誰とも食事に行っていない。
「わたし、独りで死んでいくのね、さみしいわ」
クニちゃんは、わずかに音をたててお茶をすする。磯子は微笑みを返すしかない。
しばらく世間話をして、次の訪問先に向かった。
駅を出て、商店街を通り抜けると、マンションのあいだに挟まれた一軒家がある。築50年以上の木造二階建て。
「ごめんください」
玄関の引き戸の前で磯子は大きな声を出す。反応がない。磯子は引き戸を開け、薄暗い家の中に入る。
「なんだい?」
野村修平は玄関先で腕を組んで立っていた。
「磯子です。訪問に参りました」
「ああ、そうか。もう、一週間経つのか。今日は、何日だっけ?」
「十八日です」
「まあ、あがんな。磯子さん、タバコ持ってるかい?」
磯子は、セブンスターを一本渡した。野村はタバコを手に持ちながら、かかとの上げ下げを始める。
「磯子さん、この体操はね、ヒップの形を保つのにいいんだよ」
磯子はあっけにとられ野村を眺める。
「私はね、昔は仮面ライダーみたいな胸をしていたんだ」
「そう言われてみると、厚い胸板をしていますね。昔は逆三角形だったんですか?」
野村は「そうだ」と答え、「昔はもててねぇ、何人もの女を泣かしたこともあるんだよ」と言った。
「僕も、前の会社にいたとき――、若かった頃は、同じでした」
磯子はそう言い笑う。野村は七十五歳。訪問料は野村自身が払っている。
一週間が過ぎ、磯子はクニちゃんの家を訪ね、そのあと野村の家を訪問した。磯子が玄関の引き戸を開けると、野村は椅子に座り本を読んでいた。
「磯子さんかい? あがんな」
野村は本に栞をはさみ、磯子に椅子を勧めた。
「この本はね、何度読んでも感動するよ」
机の上に置かれた本は、『クォ ヴァディス』。ノーベル賞作家の作品だが、磯子は知らない。
「皇帝ネロの時代のローマが舞台でね。クリスチャン迫害の話なんだよ。クリスチャンがライオンに喰い殺されたり、火であぶられたり、残虐な場面が有名だけど、私にとって、そこはどうでもいいんだ。私が好きなところは違うページなんだよ」
「野村さんは、ただの遊び人じゃなかったんですね。僕、知性を感じちゃいましたよ、野村さんに」
「そんなことは、言わんでよろしい。ところでさぁ、磯子さんに見せたいものがあるんだよ」
磯子が「なんですか?」と訊く前に、野村は立ち上がり、階段を昇っていった。初めて二階に上がった磯子は、奥の部屋の襖を開けた。そこには学習机が置かれ、英語の辞書とノートが載っていた。向かい側にはベッドがあり、壁にはビートルズのポスターが貼ってあった。磯子は、野村がこの部屋の主の話しをするのを待っていると、野村は一階に降りていった。
「人間は、誰でも間違いを起こす。それに気づく人もいるわけだし、このままではいけないと、わかっていてもどうにもならないでいる人もいる。人間が変わるとき、そのきっかけって、なんだと思う?」
野村は、『クォ ヴァディス』を手に取り、磯子に尋ねた。
「親とか、誰かから叱られたとか、注意されたときですか?」
「確かにそうだ。人間は忠告されると省みる。だが、もうひとつある。それはね、愛だよ。愛といっても、セックス目当てのエロスじゃダメだ。損得抜きの本物の愛を受けたとき、人間は自分の進む方向が間違っていたことに気づいて、変わることができるんだよ。心の奥底に本物の愛が根を下ろした人は、どんなに険しい道でも突き進んでいけるのさ。この本のなかで、私が好きなところは、そういうところだ」
「僕には、よくわかりませんけど、こんど読んでみます」
「そうするといいよ」
野村は磯子に煎餅を勧める。
「野村さんもどうぞ」
「私はいらない。最近、食べる量が少なくなってね。ご飯はピンポン球一個くらい食べただけで、腹いっぱいになるんだ。……年かもしれないな」
野村はそう言い、トイレに立った。
十五分経っても、野村は戻って来ない。磯子はいやな予感がして、様子を見に行くと、野村はうずくまっていた。動けそうもない。便器には、黒色の便とコーヒー色をした嘔吐物が浮んでいる。磯子は救急車を呼び、病院まで同乗した。
野村に頼まれ、磯子は荷物を取りに戻ると、玄関の前に中年男性が立っていた。値段の高そうなスーツにゴールドのブレスレットをつけているが、お世辞にもセンスがいいとはいえない。
「失礼ですが……」
磯子が尋ねる。
「三十年前に、この家を出た野村隼人です。父に会いに戻ってきました」
男は答える。磯子は事情を説明すると、男が「僕も病院に行ってもいいですか」と訊くので、「もちろん」と答えた。病院に向かうタクシーの中で隼人は、中学校のとき家出をしたこと、当時、不良グループの仲間と付き合いがあり、思いついた悪事はすべて行ったことを話した。
「僕はろくでもない人間ですよ。遊び呆けて、いまは借金だらけ。取立てに追われているんです。逃げるように帰ってきたんですよ」
磯子は「そうですか……」と答えた。
隼人が病室に入ると、野村は「おかえり、隼人」と叫ぶ。隼人が近寄ると、野村は何度も「ありがとう」と繰り返した。
それから、何回か隼人は面会に訪れた。
「父は人に縛られるのが嫌いで自由に生きてきました。後になって知ったのですが、母は僕が家を出てまもなく死んだようです。結局、父は独りで生きることになったわけです」
「でも、人は一人で生きていたとしても、独りきりでは生きていけないものです。僕は、野村さんと話をして、息子であるあなたへの想いを、野村さんから感じたことがあります」
磯子がそう言うと、隼人は「そうですか」と呟いた。
「再会したとき、父は僕に『お帰り』と言いました。僕が家を出たことは、ひとことも責めませんでした」
野村が入院してから三週間後、病院から隼人のところに、野村の意識がなくなったとの連絡が入る。隼人は病室に駆けつける。野村は、隼人の到着を確認するかのように、静かに息を引き取った。
落着いた頃を見計らい、磯子は野村の家を訪ねた。遺品の整理も終わり、家の中は片付いている。
「父が、いろいろとお世話になりました。僕は、これからはまじめに、働くことにしました。借金も少しずつ返していくつもりです」
隼人は深々と頭を下げた。
「そうですか。収入の多少に関わらず、働くことは素敵なことです。ところで、どちらにお勤めが決まったのですか?」
「電機メーカーの芝通です。職場は芝通の多摩工場というところです。工場で作業をするのが僕の仕事です」
「それはよかった。芝通は、いい会社です」
磯子は呟き、次の訪問先に向かった。
|