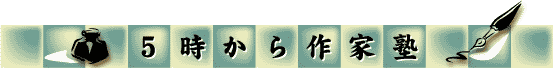第3章 何はなくとも今のあなたが
|
|
――深刻な不景気編 '96〜
|
4.主任になっても部下はゼロ
1980年代、芝通の組織はピラミッド型だった。頂点には社長が立ち、役員、役職者と続く。下に行くほど人数が多くなるわけだ。ところで、ひとことで役職者といっても事業本部長、事業部長、技師長、部長、次長、課長、ざっと挙げただけでも、これほどの種類がある。
「大学卒なら、たいてい課長くらいにはなれるよ、定年までにはね」
そうおっしゃる輩もいたが、1996年、部課長制が廃止され、だいぶ事情が変った。その話しはまた後ほどということで、今回は、入社後最初に通過する「主任」についてのお話し。
*
高木が会社から戻り、マンションの鍵を開けると、電気がついていた。朝、家を出るとき消したはずなのに、あるいは、消し忘れて出かけたのかもしれない。最近、忙しいせいか、仕事以外のことに気が回らない。靴を脱ぎ、キッチンにあがると、人の気配がする。忍び足で奥にある部屋を覗いてみると、同期の近田が待っていた。
「おかえりなさい」
近田はソファーに腰掛け、高木に笑みを投げる。高木は言葉を失い、口を開けて突っ立っている。
「勝手に上がりこんですみません。コーヒーがいいですか、お茶にしますか」
高木には近田が危害を加えるとは思えなかったが、どうやって入ってきたのか考えているうちに気味が悪くなり、ドアの外に出ようと、踵を返す。
「待ってください。近田は、襲ったりはしません。ただ、高木さんに用事があって、訪ねてきただけです」
近田はコーヒーカップをテーブルの上に置くが、高木はというと、会社帰りに買ったコンビニ弁当を下げたままである。
「今日は社員食堂に行く時間がなくて、夕食を食べそこなったんだけど。これから食べてもいい?」
「どうぞ遠慮なさらずに。ここは高木さんの部屋ですから、さあ、お座りください」
近田はコーヒーをすする。
「ところで、さっき近田君は『用事がある』って言ってたけど、なに?」
高木は、のりべんの蓋を開け、ちくわの磯辺揚げを口に入れる。
「近田がここへ参ったのは――。高木さんのことを心配したからなのです」
「僕が? 僕は、なにも心配されるようなことなんてないよ」
高木はそう言い終えると、今まで忘れていた事にふと気づく。
「明日は辞令発表。もしかして、そのこと?」
高木がそう言うと、近田はゆっくりと首を縦にふった。
今年で勤続15年の高木であるが、多摩工場の同期で主任になっていないのは、高木と近田と小林みどりの三人だけである。
勤続10年で、村上、大久保たち数名が主任になった。四年制大学卒の最短コースである。
「まあ、卒業した大学も僕よりワンランク上だし、仕事もできるし、当然のことだよね」
高木は気にも留めていなかった。その二年後、山田祐子が主任になった。
「山田さんは海外で仕事を成功させたし、結果も出してるし……、能力からいえば当然、僕は納得できた。おまけに女子大卒だし。まあ、それは関係のないことだけど」
高木は笑顔を見せる。芝通では男女平等が根付いてきている。とはいえ、正直なところ高木は女性に先を越され複雑だったのだ。
「去年のことです――」
近田は、高木の瞳の奥を覗き込む。
「高木さんの二年後輩の荒川由美子さんが主任になりました。荒川さんは、ISDNが今の形に整う前から、デジタル通信網対応ファクシミリの開発に携わっていましたし、その後も通信技術の開発に貢献してますし、実力もあります。しかし、二年後輩の女性に抜かれたこと、高木さんにはこたえたのですね」
「なんか、話しを聞いているうちに、のりべんがすごくまずくなってきたような……」
「それは、それは。なにぶん近田は気がきかないもので、気分を害したのなら謝ります。でも、近田は、高木さんのことをバカにしているわけではありません。むしろ尊敬しています。高木さんは、ずっと、蛍光灯の設計に携わってらっしゃいました。他所の応援だって、上司に頼まれればイヤな顔ひとつせず快く引き受け、みんなが行きたがらない、田舎町への出張にも自ら進んで行ったのを知っています。結果の見えない地味な仕事がどれだけ精神的に負担のかかるものか、いくぶん頭の悪い近田でも、わかっているつもりです」
近田は話しを続ける。
「なのに、上司たちは高木さんのまじめな仕事ぶりを正当に評価したとも思えません。その上、高木さんのことを軽んじさえするのです。出世しなくとも、認められなくとも、ひとことも愚痴をこぼさず今日までやってきた高木さんを、近田は尊敬しているのです」
高木は近田が淹れたコーヒーをすする。口の中に残ったのりの風味と混ざり合い、吐き出しそうになる。
「とはいってもさあ、近田君。成果のみえる仕事を要領良く掴んで、努力して、結果を出した奴が、芝通では勝ちだ。僕は負け組さ」
「高木さんがそう思われるのは自由です。ただ、高木さんの努力を高木さんの気づかないところで、見て、評価している者もいるということだけは覚えていて欲しいのです」
「近田君がここにやってきたのは、それを僕に伝えるためなの?」
「それもあります。しかし、もうひとつ、お伝えしたいことがあります」
「いったい、なに?」
「近田にお任せください! きっと、今回は高木さんも主任になれます」
「そんなことがあるはずない! どうせ、あと二年くらいは、このまま主任になれそうもないし……。だから、もうその話題には触れないで欲しいんだ」
「そうですか。残念です。仕方ありません。では、失礼します」
近田は、そう言うと、部屋の外に出て行ってしまった。高木は見送ろうとして後を追ったが、近田の姿はなかった。部屋に戻るとテーブルの上には、ふたつ、飲みかけのコーヒーが残っている。
翌日、職場でグループミーティングが開かれた。
「今年、うちの部で、主任に昇格するのは……」
上司が、高木ではない別の人の名前をあげる。がっかりしないためには期待しないこと。高木は意識して、五年前に行ったハワイ旅行のことを思い出した。
「ところで、高木さん。今年はあなたも名前が入っているから」
高木は顔を上げる。
「高木さん、夢じゃないんだから。そんな『信じらない』っていう顔しないでよ。とにかく、昇格おめでとう」
高木は我に返り、「どうぞよろしくお願いします」と頭を下げた。
昼休み、高木は近田に会った。
「近田君、きのうはどうもありがとう。おかげで主任になれるよ」
「きのう? なにぶん近田は頭が悪いもので何のことだか……。近田は、おとといから福岡に出張しておりまして、さきほど帰ってきたばかりなのです」
「じゃあ、きのうの夜は?」
「福岡でラーメンを食べておりました。ラーメンは近田の好物です」
近田は一礼をすると、自分の席へ戻って行った。高木も席に戻る。夕べのことを思い出す。確かに、近田は来たはずだ。
高木はそれ以上深く考えるのをやめ、仕事を始めた。
四月一日、予定通り高木は主任になったが、席は今までと同じで変らない。人員削減の折、高木の部署には、五年以上新入社員の配属がない。いちばん出口に近い末席に座る高木に、部下はいない。
|