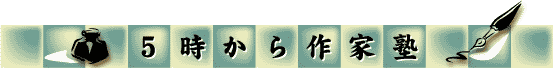| 第2章 なにぶん景気が悪いもので |
|
――バブル崩壊直後編 '90〜'95
|
9.困難こそ恵み?
一向に景気が回復しない1993年10月。
『芝通、今期1-2割の減益 電算機・家電の不振響く』
経常利益の大幅減、人員削減計画、リストラ、新聞は電機メーカー各社の不振ぶりを伝えていた。
「電話事業部って、ずっと赤字続きでしょ? 今年あたり危ないらしいですよ」
「電話も危ないけど、R&D費削減が決まったら、研究所でも潰されるとこが出てくるらしいよ」
ある日の昼休み、磯子やみどりたちは、食事も終えて、雑誌の特集さながら『危ない事業部とその理由』を情報交換していた。
「僕たちファクシミリは大丈夫。芝通多摩工場の中で、利益は高いほうに入っているもんな」
磯子には余裕の表情が浮かんでいる。
午後になり、連絡事項があるとのことで、フロアーに人が集められる。
「きょうは、皆さんに大切なことをお伝えしなければなりません」
ファクシミリ設計部々長の茂上が前に立つ。別人のように表情を硬くしている。
「実は――。大変申し上げにくいことですが……。我々、芝通ファクシミリは、九月いっぱいで、市場から撤退することとなりました。来月から、みなさんは子会社の芝電気に出向となります」
一瞬の沈黙。
「もしかして、これってリストラ?」
みどりが磯子に囁く。リストラといっても、ファクシミリ事業部まとめての切り離し。
「どうしてファクシミリ事業部なんだ?」
あたりは騒然とした。
「皆さんは、三年後、芝通に戻れる予定ですから心配しないでください」
しかし――、茂上はマレーシアにある子会社の社長に就任、課長以上の役職者は戻れないことが決まっていた。
次の日、みどりは三十七度の熱が出る。普段なら薬も飲まずに出社するのだが、ベッドから抜け出せない。
夕方、一本の電話があった。
「飲みに行かない?」
山田祐子である。俄然、身体が軽くなったみどりは、待ち合わせの店に向かう。
「なんか、かっこ悪いよね、私」
みどりは、ビールの泡を見つめ呟く。
「そんなことないよ、まあこういうときは飲まなきゃ!」
祐子は、ビールを飲み干し、みどりの分までサワーを注文する。みどりのビールはなかなか減らない。
「私はね、私が開発した技術が残ればそれで幸せだと思ってた。仕事は面白いし、毎日が楽しいし。なにより開発した製品が出荷される時の満足感て、なんともいえないでしょ?」
祐子は、黙って頷く。
「なのによ、芝通のファックスが潰れちゃうんだよ。『今までお前がしてきたことは間違いだった』って突きつけられちゃって。どこがよくなかったの? どうすればよかったの? これから、どうしていけばいいの? 会社、やめたくなっちゃったよ」
<まあ、まあ>
祐子はそう言おうとしてやめた。出向命令を受けたことのない自分には、頭ではみどりの悲しさを理解できても、心の奥底ではわかりきれないからだ。
「私はファクシミリが好きなの。仕事を一生懸命やって幸せだったし、いい思い出にもなった。けど、結局芝通は私に何も残してくれなかったと思わない? 最後は『君はいなくてもいい』って、言われちゃったわけだし……。ちょっと、ひどすぎ」
「でも、芝通に限らず、なんだってそういうところはあるんじゃないの? モノに期待して、ヒトにすがりついて、拝み倒したって見返りなんてないよ。最初からそのつもりでいると楽だよ。仕事でも何でも『ほどよく』が一番なんだなって、最近思うようになったのよ。年取ったのかな?」
みどりは時計に目をやると、十二時をまわっていた。もう少し飲みたい気分のみどり。二人は次の店に移った。
一週間が過ぎた。みどりの有給休暇は残っている。三日前、目覚し時計の電池が切れたのだが、そのまま替えていない。
みどりはベッドから抜け出し、みのもんたのお昼の番組を見ながらコンビニ弁当を食べる。昼寝をしてテレビを見て一日が終わる。芝通は、みどりがいなくても、きのうと変わらず動いている。誰が欠けても、芝通は潰れない。
その夜遅く、みどりのところに父親から電話があった。初めてのことである。一年で盆と暮れしか会わないし、みどりの部屋を訪ねて来てくれたこともない。
「元気でやってるのか?」
父親は、言葉少なく母や妹の様子を口にした。
「みんな元気でなにより。私も元気だよ」
みどりは、めいっぱいの嘘をつく。
「私ね、今まで気がつかなかったけど、私って、恵まれていたのよね。なのに感謝もなく生きてきたの。芝通で仕事があることって、当たり前だと思ってた。最近、初めて気づいたのよ。自分が恵まれていたってことに」
父親は、なにも詮索することなく、「そうか」とだけ答える。
「人の幸せってなんだと思う? 貴族のように優雅で贅沢な暮らしをすること? 人によってそれぞれだと思うけど、ただ、一ついえることは、物事がうまくいっているときよりも、困難にぶち当たったときのほうが、人は考えるでしょ。だから、いろんなことに気づいて成長するのよ。そう思うと、時にはつらいこともあったほうがいいのかもね」
父親は、「たまには帰って来いよ」と言い、電話を切った。
翌日、みどりは出勤した。あたりは騒がしく、仕事をする者はいない。
「独身は気楽でいいよな」
磯子は、みどりにそう言いながら席に着く。
「好きで独身やってるんじゃないんですけどね」
「問題はりさ子だよ。りさ子になんて言えばいいんだ?」
磯子は頭を抱える。
「子会社に出向だなんて言ったら、りさ子は『期待に応えられない駄目なヤツ』って僕の額に烙印を押して、ポイするんだろうな。りさ子は僕が芝通で出世することを夢見て結婚したわけだし……。思えば昔から、僕ってついてない男なのさ。雨男だし。小学校の運動会は、五回も雨。たった一回だけ晴れた年があったけど、その年僕は、喘息で休んでたわけ。中学校は、入学するなり水ぼうそうにかかって、『ボツボツ君』ってあだ名つけられていじめられたし。僕って、ダメじゃん。猫がソファーにもらしたウンコの上に座って、お尻にウンコをつけて、友達の家に遊びに行って。友達少ないのに最後はいなくなっちゃってさ」
磯子は溜息をつく。
「りさ子が愛してるのは、僕じゃないのさ。彼女は、自分の思い描く結婚生活を愛しているんだよ」
「本当にそうですか?」
「世の中、りさ子みたいな生き方をする女性のほうが得をするんだ。僕は彼女を失うのが怖くて、必死に働いて来たのさ。でも、もう全てが終わりだ。りさ子は仕事をしているから、働く時間を増やせば僕がいなくても生きていけるしな」
「たとえ、りさ子さんが磯子さんのこと、『必要ない』って捨てたとしても、きっとどこかで誰かが、磯子さんのことを認めてますよ。人は必ず誰かに愛されているものですよ。それに気づくかどうかは別として」
「そーか?」
「まあ、先のことを悩んでも、変わらないですよ。ソファーにウンチもらした猫のこと、思い出してみてくださいな。何も考えてませんよ。それでも、いつだって、餌にありつけるし、気ままに生きてるでしょ? りさ子さんに捨てられるのも決まったわけじゃないし。明日のことを思って悶々とするより、今できることをしましょうよ」
「小林さんは、吹っ切れたんだ。うらやましいな」
磯子は呟く。
数日後、出向先での職場が決まる。みどりは神田のオフィスで、磯子は静岡の研究所で働くことになった。
「そろそろ、りさ子に言わなきゃいけないな」
磯子は家に帰り、りさ子に出向することを告げる。
「それでさあ、勤務地は静岡なんだけど、一緒に来て欲しいんだ」
「私、田舎はイヤ。あなた一人で行ってちょうだい」
りさ子はそれだけ答えると、「もう、眠いから」と言って寝室へ消えた。
磯子は単身で出向することにはなったが、離婚は免れたようである。
「ほら、捨てられなかったでしょ。りさ子さんは、計算高そうに見えるけど、純粋に磯子さんのことが好きっていう部分もあるんですよ、きっと」
「そうかなぁ? りさ子は、『ついてく』とは言ってくれなかったけど……。まぁ、よかったのかもしれないなぁ」
磯子はうれしそうにしている。
「どうして、よかったんですか?」
「……だってさぁ、単身なら、向こうでやりたい放題じゃん!」
磯子は、鼻歌を歌いながら、静岡のガイドブックを開く。
「磯子さん、静岡に行くことを、けっこう楽しみにしてません?」
「わかる? 地元の女の子と仲良くなって、サッカー観戦に誘って、帰りに飲みに行って、そのまま勢いで……」
変わり身の早い磯子である。
『生命の本質とは、自分で自分のコピーを作ること』
それを貫くのは良いのだが、いずれ悪行はばれるものである?
|