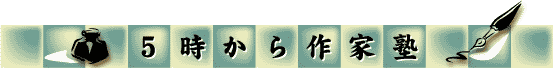| 第2章 なにぶん景気が悪いもので |
|
――バブル崩壊直後編 '90〜'95
|
7.シリコンバレー午前零時
光伝送システム設計課は、光ファイバーケーブルを使った通信システムの開発を受注した。通信事業者からの発注を、電機メーカー数社が分担して開発にあたっている。
芝通のエンジニアは七人がひとつのグループになり、三ヶ月交代で、アメリカ西海岸のシリコンバレー近くの拠点で働いている。シリコンバレーには、世界中の電子企業の多くが密集しているが、芝通の拠点は、そこから南下した、LA郊外にあった。
アメリカでの生活は快適である。西海岸の過ごしやすい気候、安い物価。住まいは一軒家を七人でシェアしている。庭は芝生の緑が綺麗で、ミニサッカーができるくらいの広さ。玄関のドアを開けると、ダンスができるほどのリビングがあって、芝通アメリカ社製の大型テレビとビデオが置かれている。一人一室ずつを使って生活しているが、どの部屋も十畳以上で、トイレもシャワーも各部屋にある。
主任の鳥井は、日本では、築十八年/2DKの社宅に、家族四人で住んでいる。一階なので日当たりは悪いし、ゴキブリもいる。出張先で日本の社宅を思い出すと、早く家族のもとに帰りたい気持と、ここを離れたくない気持とが、交互に現れて複雑になる。
芝通従業員の住宅事情はさておき、今回は、光伝送システム設計課のアメリカ出張先で起こった怖いお話し。
*
山田祐子はベッドの中で夢を見ていた。実験室の真ん中に置かれている試作品「L42」を眺めている。端末用の電話機が鳴る。リングパターンからすると内線からの呼出し。
<外線からの着信なのに、おかしい>
祐子はバグに気づき、プログラムを修正しようとする。なのに、開発に必要な道具がどこにもない。
<どうしよう。バグが修正できない。納期、納期、納期……。そうか、私は出張中だった。ここはカリフォルニア州……>
そこで目が覚めた。部屋の電話が鳴っている。内線呼出し。同じ家の別の部屋からの電話だ。
「もしもし、鈴木だけど落着いて聞いて欲しい」
祐子がリビングに下りていくと、村上はテーブルに両肘をつき、うなだれていた。村上の向かいには、鈴木と安部が腰掛けている。アメリカに来た時は七人だったメンバー。週末ごとに、ひとりずつ欠けていき、今は四人になってしまった。
祐子は、今回の出張にはいやな予感があった。「行っちゃダメ」と心のどこかで警笛が鳴るのを振り払って日本を離れたのだ。
*
三週間ほど前、最初の事故は起きた。アメリカ出張グループの一人である水田は、妻が病気になり、日本に帰国することとなる。まだ時差ボケも治らない頃、瓦を補修するために自宅の屋根に登っていた。作業をしている最中に足を滑らせ、首の骨を折り死んでしまったのだ。祐子たちは単なる事故だと思っていたし、遠く離れた日本で起きたことなので、実感も湧かなかった。
それから一週間後――。出張メンバーの中には、佐久間が加わっていた。祐子は、日本にいたとき、佐久間に小バカにされたことがあったので、佐久間のことを快く思っていなかった。しかし、異国で仕事をしていくうちに日本人同士の結束が固まり、二人ともお互いを認め合って仕事をするようになっていた。
土曜日、佐久間は同僚の安部と二人で飲みに行った。その帰り道、暴漢に襲わて刺され、病院に運ばれたのだった。安部は軽い怪我ですみ、二日間で退院できたが、佐久間は刺された日の翌未明、命を落としたのである。
この時点で、七名いたメンバーは五名になった。
「神様は、人の命を持っていくときは、ひとひねりで持ってってしまうのね」
立て続けの事故死に、気を引き締めるようにと、技師長からのお達しもあった矢先、今回の交通事故が起きたのだ。
鈴木の話によると――。土曜日の朝、鳥井は一人で車に乗り、時速百キロメートルものスピードでドライブをしていた。アメリカは右側通行である。左折をした時、右側車線に入らなくてはいけないものを、日本にいた時の習慣で左側車線に入ってしまった。前方に猛スピードの車が見えたときは遅く、正面からぶつかり車は大破した。鳥井の死も、このアメリカ出張に絡んでいることは否定できない。
祐子、村上、鈴木、安部。残された四人は沈み込んだままである。
「今回のアメリカ出張に絡んだ人が、次々に死んでいってますよね」
鈴木はそう言って、それぞれの顔を見た。
<次は自分?>
祐子はつい考えてしまう。
「そういえば、日本を発つ前から兆候はありましたよ」
出発の一ヶ月前、村上は高速道路を時速百五十キロメートルで飛ばしていたところ、ネズミトリに引っ掛かって一発免停になり、さらに海でメガネを流し、コンサートに行った帰りには財布を盗まれた。
祐子は、立て続けに村上に悪いことが起こるので、心配になったことを思い出す。
鈴木も、出発の二週間前、ある企業の株価が暴落して大損し、翌日、会社のガラス戸に台車ごと突っ込んで軽い怪我をしたことを語る。
「安部さんは、先週、刺されたでしょ? じゃぁ、悪いことが起こっていないのは、私だけ? ということは、次は、私? 私が死ぬの?」
祐子は、アメリカ人男性数人に囲まれ、かわるがわるレイプされ首を絞め殺される自分を想像し、そんな死に方だけはイヤだと思った。日本に帰りたい。でも、死ぬことが決まった人は、どこに行っても避けられないだろう。水田のように、死ぬ時は死ぬのだ。
その晩、祐子は眠れなかった。目を閉じると、見てもいないのに、鳥井の車が左車線に入っていくところが鮮明に浮かぶ。大破した車の中で、鳥井はぐったりと首をうなだれ、顔じゅう血まみれになっている。どす黒い血が筋になって道路を流れていく。
なんとか眠りについた午前二時頃、部屋のドアが開く音が聞こえる。鍵はかけたはずなのだが。祐子はベッドの足元に目をやる。そこには、日本にいるはずの課長の渡利が立っていた。
「なんで課長が?!」
祐子は声をうわずらせる。
「どうしてかな?」
渡利は答え、消えた。真夜中の部屋には、まだ渡利の気配が残っているようでもある。佐久間が亡くなったあと、渡利は様子を見に、祐子たちのところに来る予定でいた。厳しく管理責任を問われたため、渡米せざるを得なくなったのだ。本人は「行きたくない」とまわりにこぼしていた矢先、胃潰瘍で入院し、出張は取りやめになった。
部屋のドアが閉まる音がする。しかし、音だけでドアは開きも閉まりもしていない。祐子は怯え、部屋の電話から村上の部屋に電話し、外が明るくなるまで喋りつづけた。
木曜日になり、祐子たちは仕事に戻る。納期に対する遅れは許されない。一人しか女性がいないので、帰るときには女子トイレや更衣室を、祐子が戸締りすることになっている。蛍光灯のスイッチをオフにするたび部屋は真っ暗になる。独りきりの祐子は、暗くなった部屋を振り返らないように、早足で廊下に出る。実験室の前を左に曲がり、薄暗いまっすぐな廊下を歩く。靴の音が壁に跳ね返って響く。コツコツというテンポが速まる。
「あれっ?!」
祐子は足を止める。暗くてはっきりしないが、出口のガラス戸の向こうに男が立っているのが見える。祐子は金縛りに遭ったように動けない。男は、「次は、お前だ」と言いたげに、ゆっくりと右手をあげ、祐子を指差す。
「イヤ!」
男は出口のドアに手をかけ、開こうとしている。
「こっちに来ないで!」
祐子が叫ぶ。ドアが開く。
「早く、来いよ。おいてくぞぉー」
ドアの向こうにいたのは安部である。祐子は、その場でへたりこみそうになるのをこらえ、出口まで歩いた。
その週の土曜日、四人はリビングに集まり、朝まで飲むことにした。午前零時、急に安部が泣き出した。
「なんで佐久間が死んで、オレが助かったんだろう? オレには、わからない。オレの命はオレのものなのに、オレにはどうしようもできないのが悔しいよ。でも、死ぬのは怖いんだ」
飲んだ席で泣くなんて、芝通では滅多にない。
「私ね、アメリカに来てから、まわりの人が次々に死んでいったでしょ。それで、思ったの。私たちは、地球に生まれついて、三方向に広がった空間とひとつの時間のなかで暮らしているでしょ? でも、どこかすごく遠いところには、時間が止まっているのに、遠くまで自由に動けるような場所とかがあるんじゃないかと思うの」
「重力が強ければ時間が止まることはあり得るけれど、同時に自由というのは矛盾しているような気もするけど……」
物理学科出身の鈴木はこだわる。
「私たちの思うところのいっさいを、はるかに越えたところでの話しよ。私が言いたいのは、死んだあとで永遠や自由が手に入るところに行くとしたら、みんな死ぬことを選んじゃうでしょ。だから、遺伝子が地球で残っていくために、死ぬことは怖いことって人間の頭にプログラミングしたのよ、きっと。私たちは、死にたくないって思うように、プログラムされているだけ、だから私は死んでも大丈夫だ、って自分に言い聞かせているのよ」
「でも、死ぬのは怖いよ」
と鈴木が言う。祐子は否定しなかった。
「大丈夫、もう誰も死なない」
鈴木はそう言うが、祐子は頷けなかった。
その後、四人は週末の外出禁止を守り、無事帰国の日を迎えることができた。
日本に帰ると、課の人達は、生還した宇宙戦艦ヤマトを迎えるような喜びようであった。入院中の渡利も喜んでいるとの話が入り、四人は見舞いに寄った。
祐子は病室に入り、渡利の近くまで歩く。変わり果てた姿に、祐子は言葉が出ない。出張前に会ったときは、ふっくらと膨れていた頬が削げ落ち、目も窪んでいる。鼻にはチューブが通され、腕には点滴用の針が刺してある。
「本当は胃癌なんだよ。こんな姿、見せたくなかったけどね」
横で奥さんが目頭を押さえる。渡利は奥さんの肩に腕をかけ、よろけながらベッドから降りる。腕には肉がなく、皺のよった皮膚には点滴の痣がシミのようになっていた。
それからしばらくして、もう一度祐子は見舞いに行った。前よりもさらに渡利は弱っている。話しをするのも苦しそうで、祐子は渡利の口元に耳を近づけて話しを聞く。
「『L42』の開発が終わるのを、見届けられそうもないな」
甘酸っぱいような、不思議な臭いがする。人は死ぬ前に、独特の臭いを放つことがあるという。その日の夜、渡利は亡くなった。
<まだ続いている>
祐子たちのフロアーが、四階(死界)の東北(鬼門)にあるのが悪いとか、「L42」の「42」は「死人」だとか、光伝送システムの「シ」は「死」を意味するとか、まことしやかに囁かれた。
祐子たちは、課のメンバー全員で高尾山へ御祓いに行くことを命じられた。クリスチャンである鈴木は「行けません」と言いだし、一時騒然となったが、自由参加ということで落着いた。
四月の組織改正で光伝送システム課は分割され、四階の東北の場所は書棚になった。
半年ほどのあいだに四人もの命がなくなったのだが、「L42」の開発は中止になるどころか、エンジニアを補充するなどの対応が功を奏し、遅れも出さずに進んでいる。
「おはようございま〜す」
今年もフロアに新入社員の声が響く。
亡くなった人たちの仕事の穴を埋めることは、他の人にもできる。
しかし、誰がどんなに願っても、亡くなった人には、もう二度と会うことはできない――誰もがたった一つの存在なのだから。
|