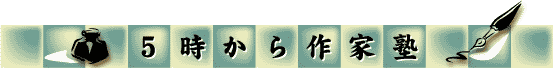| 第2章 なにぶん景気が悪いもので |
|
――バブル崩壊直後編 '90〜'95
|
1.最初に下がったものは年収
「なにぶん景気が悪くなったもので」
芝通多摩工場に残業規制がかかったのは、1990年のことだった。最初は、品質保証部やサービス部といったスタッフ部門だけ、一ヶ月の残業時間の上限が決められた。
「『トリプル安』とか、マスコミは騒いでるけど、景気なんてすぐ回復するよね、きっと。だって、円高不況のときの残業規制は半年で解除になったでしょ。今回だって同じ、どうせすぐに終わるわよ」
電話機設計部の関口ルミ子は友人に漏らす。
バブルが崩壊したといっても、仕事は相変わらず忙しい設計部門。不景気なんて、他人事のように考えていた。しかし――。
*
関口ルミ子は、銀行のキャッシュディスペンサーの前で固まっていた。
「残高122円! 給料日まで、あと十日もあるっていうのに。どーやって暮せってんじゃい!?」
主婦が一万円札数枚を財布にしまいこんでいる。
<あのお金があったらどんなにいいだろう。あとをつけていって、人気のないところでひったくっちゃおうかな>
ルミ子はそんなことを考えつつ、銀行を後にした。
1991年、新製品の開発が終わり、ほっとした矢先のことだった。
「景気後退のため、我々、電話機設計部門も一ヶ月の残業時間は一人平均四十時間以内と決まりました」
突然の残業規制。いままでは月に最低六十時間、納期が迫ると八十時間以上残業してきた。仕事は変わらないのに、どうやって残業時間を減らすのだろうか?
「その件につきましては――。関口さんたちは、新機種の開発が終わったばかりで、次の納期まで間がありますよね。悪いけど、納期が迫った人たちに、残業時間をまわしてもらえませんか? 課の残業を平均四十時間に抑えるには、関口さんたちの協力が必要なんです」
急ぎの仕事をやっている人に、そうでない人が残業時間を分けてやってくれないか、ということだ。
「十時間までにしろだって? そりゃあ、課長はいいですよね! 私の場合、銀行に振り込まれる給料の三分の一くらいは残業手当てなんですよ!」
ルミ子が責めても、「まぁ、私が決めたことではないので……」とあいまいな答えが返って来るばかりである。
やむなく残業を十時間以下に抑えたのだが、「節約」なんてまるで無縁のルミ子。行き着いたところは――、銀行残高122円。小学生だってもっと貯金があるというのに。社内預金も株もないルミ子には明日がない。いや、今日食べるものすらない。どうやって十日ものあいだ、命を繋ぐのであろうか?
*
残業手当てが減って、切羽詰った人はルミ子だけではなかった。
例えば、磯子周一。1990年9月、結婚が決まり、マンションを購入した。
「貯金の利子よりマンションの値上がり額のほうが高いのよ。二十年もすれば、マンションは倍以上の値段になっているわ」
磯子夫妻は、バブルが崩壊したことに実感がなく、土地価格も給料も上昇しつづけると信じていた。モデルルームのシステムキッチンの扉を開ける婚約者の横顔。今まで、年収は下がったことはない。その計算でいくと、なんの問題もないはずだった。
それから一年、突然の残業規制。基本給はアップしているが、月々の手取りは減っている。磯子家、ローン返済のピンチである。詳しいお話は、第六節でするとして――。
世のなかには、ローン返済のためパートに出た妻が、職場の男性と不倫して崩壊する家庭もあり、社会復帰した妻が夫に見切りをつけて家を出る場合もあり、たかだか残業規制というものの、その為に大きく道を外した人もいたようである。
*
武蔵テックの沼田はベッドの中で爆睡中であった。電話が鳴っている。時計を見ると午前十時半。
<土曜日の早朝?に電話をかけてくる非常識な奴は誰だぁ?>
と受話器に手を伸ばす。
「今日ひま? 赤坂に行かない?」
取引先である芝通の関口ルミ子である。
武蔵テックは東京の外れにある。沼田は大学卒業後、田舎から出てきて一年になるが、忙しいこともあって都心で遊んだことがない。先月、実験室でルミ子にその話をしたとき、
「この製品の開発が終わったら、赤坂に連れてってあげる」
と言われたのである。ルミ子とは、製品の打ち上げ会で飲んだことはあるが、二人で行くなんて期待もしていなかった。
「どこで待ち合わせます?」
「じゃぁ、うちまで車で迎えに来てくれる? 今日は電車に乗りたくない気分なの」
沼田は、ルミ子の銀行残高なんて知りもしない。急いで支度をして車に乗った。
沼田たちは、昼食を食べ、店を出る。お金を出したのは沼田である。
<都会で暮らす女性は、デートの時は男性にお金を出させるものなのかもしれない>
沼田はそう思いながら赤坂の高層ビルのそばを歩く。ルミ子は、都会に慣れない沼田に、ビルの名前を教え、美味しいお店の話をする。
<仕事のときは厳しいが、プライベートでは優しい人なのかもしれない>
沼田はそう思った。
ルミ子は沼田に寄り添い、腕を絡める。
「あたしはね、甘いものが大好きなの、あなたは?」
「僕は、どちらかというと、甘いものは苦手ですね。お酒のほうが好きです」
「そう。それはそうと、ねぇ、ホテルに行かない?」
「ホテル?」
「そこよ」
ルミ子は向かいの建物を指差す。
<都会の女性は積極的だと聞いてはいたが、初めてのデートなのにいいものか、でも、断ったら失礼じゃないか、やってもいいって言ってることだし……、ならば>
「やはり、お部屋はツインですか? それとも、ダブルですか?」
「はぁ?」
「だから……、ホテルの部屋は……」
ルミ子は腕を放して、笑い出す。
「そうじゃなくって、ホテルのデザートバイキング。あたしは甘いものが大好きだって言ったでしょ。ケーキとか、アイスクリームとか、クレープとか食べ放題の店がそこのホテルのなかにあるのよ」
なにを勘違いしているの? と言いたげなルミ子のしたり顔。沼田がホテルのデザートバイキングのことを知らないのをわかっていて言ったに違いない。沼田は、どこまでルミ子のことを許せるか、試されているような気がした。
「もしかして、関口さんって、親しくなると、どんどん意地悪をエスカレートさせるタイプの女?」
「なにか言った?」
ルミ子は訊き返す。自分が意地悪なことをしているということはわかっている。何度も同じことを繰り返して、最後は自分も相手も疲れ果てて壊れていく。相手に無理難題を受け入れさせたい衝動を抑えられないのだ。
月曜日、沼田は芝通の実験室にいた。トイレに立ち、実験室に戻る途中、ルミ子と同じ課の女性社員とすれ違う。目が合うと、その女性は、クスッと笑って、足早に沼田のそばを通り過ぎる。次に、別の女性社員とすれ違うが、彼女も意味ありげに笑いをこらえ、沼田のそばを通り過ぎていった。
<知れ渡っている>
次の週末も、沼田のところにルミ子から電話があった。
「いいですよ」
それでも、沼田は断らずに、また行ってしまうのである。次も、ぜんぶ沼田のおごりで。
ルミ子は、残業手当が減ったピンチを沼田によって切り抜けたのであった。
|