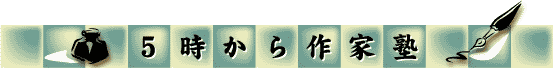| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
6.35℃/95%の世界と霧中な世界
奇数年入社は、にぎやかで遊び好きな人間が多いのだが、彼らの、その後はというと二つに分かれた。
①そのまま貫き、遊び通した人。
②本来の理科系な人間になって、エンジニアとして活躍した人。
それぞれが、どのような道をたどったのであろうか。1989年、85年入社組は五年目を迎えた。
たとえば、村上。女性の扱いにも慣れていて、おしゃれで遊び好きな人間だったが、実は、根は理科系だった。村上は入社三年目頃から、人が変わったように仕事に没頭し、光伝送システム設計課ではメインとなるシステムの開発を任され活躍している。しかし、女性に対して、まめな性格は変わってはいない。
大久保は、プライベートがない、とぼやいていたが、そのうち仕事の面白さにハマっていった。そうなると、彼女との付き合いが面倒臭く思えてくる。会う回数も減り、自然消滅。予想通り、独身エンジニアの道を進んでいる。
村上と同じ課で働く祐子の場合はどうかというと――。彼女は、男女差別体質と戦い、システムエンジニアとして開発の仕事を任されている。
1989年入社五年目、ジャパンバッシングが激しかった時代、アメリカ出張が決まる。この海外出張の背景には、電機メーカーの海外展開が関係している。1980年代後半から、各社は中国、マレーシアなどの東南アジアにも拠点を広げる一方、欧米での事業も拡大する。芝通アメリカは、本社はニューヨークに、工場はカリフォルニア州におく。祐子はシリコンバレーの近くにできた新しい拠点に行くことになったのである。アメリカ人たちは五時に帰宅するので、残業しているのは日本人ばかりである。だが、日本人も週末は充実しているようだ。
「アメリカはね、物価が安いの。ジュースより安いビールもあるし、ウイスキーなんか、信じられないくらいの値段よ。円高のせいもあるけど。ゴルフ場も破格。遊ぶところもいっぱい。今週末はグランドキャニオンに行こうかな、ビバリーヒルズにしようかな……」
アメリカに行っても、週末になると浴びるほど酒を飲み、遊んでいるところは変わっていないらしい。
では、みどりはというと――。みどりは、新入社員の頃は、桐畑の冷たさに傷ついていたが、入社五年目となるとすっかり慣れていた。化粧は手抜きでもかまわなくなり、口紅の代わりに歯磨き粉の跡を残して出勤する日もある。重さ5キロものファクシミリを両脇に抱えて運んでいるうちに、か細かったみどりの腕は、たくましくなっていった。みどりのスカートの裾に光る銀色のものは、ホチキスの針。
「ええ、ミシンがないから……」
と答えたこともあるが、ミシンがあっても、ホチキスで止めたに違いない。仕事以外のことには、時間も気も使わない人間になっていた。スカートは一年以上洗濯していない。
その頃、みどりは次機種の開発で壁にぶつかっていた。みどりが設計したファクシミリは高温高湿の条件下に置くと、原稿が詰まりやすくなるのだ。このままでは社内規格に合わず、雛形がダメを出すのは間違いなく、量産化できない。連日、みどりは恒温槽にこもって対策を考えた。槽内は温度と湿度が一定に保たれているので、真冬でも、真夏の環境に設定して実験ができるのだ。物置小屋くらいの大きさで、ひとつだけガラス窓がついている。
朝からみどりは、対策の効果を確かめるため恒温槽にいた。今週中に問題解決しないと、設計の進捗に問題が出てしまう。恒温槽の試験条件は温度35℃、湿度95%。真夏のジメジメした日と同じである。みどりのメガネが曇る。今朝、目に痛みがあったのでコンタクトレンズをつけるのをやめたのだ。みどりは、ファクシミリに原稿を十枚ほど入れコピーボタンを押す。腕に汗が滲む。やはり、原稿は詰まる。ドライバーで分解して部品にヤスリをかけ、元通りに組み立て、繰り返す。頬は赤くなり、顎から汗がしたたるが、苦ではない。もう一度コピーボタンを押す。また原稿が詰まる。
翌朝、みどりはユニットバスの洗面台の前に立って出勤の支度を始める。底にドロドロが溜まったグラスには、歯ブラシが一本だけ立っている。鏡に顔を近づけ、コンタクトレンズを入れる。ぼやけていたみどりの視界は、排水口にへばりつく黒カビや、床に散らばった髪の毛の一本までもが見えるほどに、くっきりしたものへと変わる。今朝は、ひどく目が痛む。鏡に映る白目は真っ赤に充血しているし、目ヤニも多い。瞼を指で持ち上げ、コンタクトレンズを外し、痛みを鎮めようと目を閉じた。しかし、痛みはおさまるどころか、瞼も開かなくなってしまった。しかも両眼いっぺんに。
みどりは、電話機のダイヤル5にある、盲人用の突起を頼りに、もどかしい手つきで会社の番号をダイヤルする。
「目が痛くて、何も見えません」
「いつ回復しますか?」
桐畑は事務的な口調で尋ねる。開発の進捗に決定的な問題を及ぼすようなら、応援を頼むつもりなのだろう。
「わかり次第また連絡します。あのぉー、……」
みどりは先を話そうとしたが、電話は切れていた。受話器を置いたみどりは、無性に誰かと話がしたくなる。が、祐子はアメリカに出張中で話ができない。
二年前、みどりの彼氏は「君にはついていけない」と言って去って行った。みどりのベッドで一緒に寝たら、背中が痒くなったのが言い争いのきっかけであった。
「主夫をやらされるなんて、ごめんだね。掃除くらい、きちんとやってくれる女がいいね」
と彼は言った。それ以来、みどりに彼氏はいない。
このままでは図面も描けないし、実験もできない。収入も心配であるが、誰からも必要とされなくなってしまうことが怖いのだ。『芝通の小林みどり』から『芝通』が消えた、収入もない、盲目の『小林みどり』に、なんの価値があるのだろう。
みどりは手探りで、マンションの三軒先にある眼科に向かった。
「私は、盲目のまま生きていくのですか?」
みどりは、眼科医に尋ねる。診断は角膜剥離。瞳の表面にある角膜が傷つきはがれたせいで痛みがでたらしい。朝七時から夜十一時まで規定を超えてコンタクトレンズを入れ続けたのが原因だった。レンズの手入れを怠ったのもよくなかった。
「大丈夫ですよぉ。一週間もすれば、また目が開きますよ。視力には問題ないですから。ただ目が開かないだけですよ」
そう言われても、みどりは、また目が見えるようになる気がしない。眼科の外に出ると、周りのものをつたいながら歩いた。
「小林さん、どうしたの?」
みどりは聞き覚えのある女性の声に耳を澄ます。マンションの大家の奥さんで、一階にある中華料理屋を本業にしている。みどりは目のことを話した。
「よかったら、うちの店で食べていきなよ」
みどりは朝から何も食べていない。
「遠慮しなくていいんだよ。さ、入って」
奥さんはみどりの手を引いて椅子に座らせた。しばらくすると、奥さんはお盆に中華丼を乗せ、みどりの前に置き、みどりの手にスプーンを握らせる。みどりは、手探りで中華丼をすくって口に運ぶ。ご飯が温かい。みどりはよく噛んで飲み込む。もう一口入れると、こぼれ落ちた涙が頬を伝った。
その日の夜遅く、大久保、村上、近田の三人が見舞いに来た。
「きったねぇ部屋だな。寮のオレの部屋よりきたねーよ」
大久保は流しに山積みになっているコップを見て言う。
「余計なお世話。ほっといて」
自分の声が目に響くと、痛みが走る。
「小林さん、大丈夫ですか?」
近田がみどりに尋ねる。
「ものすごーく痛いの」
「どんな?」
「生理痛の痛みというより、初めてセックスした時の痛みが近いわ」
「初めてのセックス? なにぶん近田には彼女というものがおりませんので。いくぶん頭も悪いもので、おっしゃることが理解できないのです」
近田は首をかしげる。
「要するに、ズッシーンというより、ヒリヒリ、ズキズキっていう感じかな。とにかく、ものすごーく痛いのよ。今まで一番痛かったことを思い出してみて。たぶん、それが近いはず」
「そうかぁ?」
大久保も首をかしげる。村上がコンビニ弁当の封を開けて、みどりに箸をにぎらせた。
「私、買い物にもいけないから、困ってたのよ」
みどりは、ハンバーグを箸ではさみ、大きいまま口に運ぶ。手探りでウーロン茶を飲み、唇の周りについたデミグラスソースを手の甲で拭う。村上は流しの食器を洗って、みどりが食べ終わる頃、四人分の紅茶を淹れた。
翌日から、かわるがわる同期の人間がみどりの部屋を訪ね、食料などを差し入れた。このまま、盲人として芝通を去るかもしれない『小林みどり』にだ。
「こんな、なんの価値もない私に、ありがと」
みどりは呟く。
「なにぶん近田は、頭が悪いもので、価値のない人間というものを想像することができません。たとえ収入がなくても、目が見えなくても、愛される価値はみな同じなのではないでしょうか」
「そうかもしれない……。私は『芝通の小林みどり』だから価値があると思っていたけど、それは間違いなのかも知れないわね」
一週間後、みどりの瞼は開いた。仕事に戻れる。職場は元のままだ。
「酔っ払ってコンタクトをつけたまま寝てしまったんですって? 気をつけないとだめよ」
「桜井さん、噂に尾ヒレをつけないでくださいよ」
みどりが笑い飛ばしていると、桐畑が横に来た。
「小林さんの仕事はそのままにしてあります」
応援を頼まなかったらしい。みどりは、遅れを取り戻すには何をすべきか考えた。
みどりは、実験室に向かい、ファクシミリを小脇に抱え、ドライバーをスカートのうしろポケットに差し込み、恒温槽へ向かう。温度35℃、湿度95%、ボタンを押して設定した。
このように、奇数年入社の人たちを
①そのままを貫き、遊び通した人。
②本来の理科系な人間になって、エンジニアとして活躍した人。
でわけると、圧倒的に②の道を歩んだ人が多い。しかし、①タイプな人間もいる。その話は、もっと後になってからということで……。
|