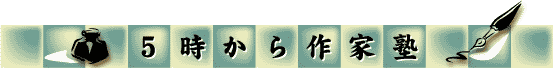| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
5.ダイエット不要、おそろしく多忙なエンジニア達
芝通の設計部門で、暇をもてあましている人はほとんどいない。入社して三年目になると、責任ある設計箇所を任されるようになる。彼らは本領を発揮し、納期をにらみながら納得いくまで仕事に没頭するのだが、開発機種によっては、人員が足りなくなる時がある。そのような場合は、開発が終わるまでのあいだ、よその課から人を借りる。これを「応援」と呼ぶ。今回は、日々忙しいエンジニアの一人――大崎と、「応援」を要請された近田の話である。近田は、大久保と同期で、入社二年目。大崎は近田の二年先輩で、二人とも大岡山にある国立大学を卒業している。
*
近田は、水筒の栓をねじり蓋に温かい麦茶を注いだ。
「お前、変わっているな。僕は自動販売機の80円コーヒーをブラックで飲むのが一番いい」
大崎は、紙コップを口に当てコーヒーをすする。一昨日から、近田は大崎の所に応援にきている。
「近田は温かい麦茶が好きです。ここの販売機では売っていませんので、家から持ってきているのです」
近田は顔にあたる湯気を堪能しながら、ゆっくりと麦茶を飲む。昼休み、喫煙室は混んでいる。
「近田君は煙草を吸わないのか?」
「はい、近田は煙草は吸いません」
大崎は、「そうか」と煙草を口にくわえ深く吸う。近田たちは朝八時半からずっと、データを取るために実験室にこもっていた。午後一時になると社員食堂が閉まるので、仕方なく昼食をとる。大崎は二ヵ月後に発売となる家庭用電話機の電気設計を担当している。
食事を済ませた大崎と近田は、音響試験室のドアを開ける。スタジオのような防音が施されているせいで、室内に空気の流れはない。
「大崎さん、この機械で何を試験するのですか?」
近田は目の前の測定器を眺めながら質問する。
「受話音量を計るんだよ」
「ジュワオンリョウ? なにぶん近田は頭が悪いもので、それだけの説明では良く理解できないのですが」
「近田君は僕と同じ大学なんだから、頭が悪いなんて言わないでほしいな」
「すいません。なにぶん、近田は人から、勉強はできるけれど頭が悪いとよく言われます」
大崎は微笑み、近田に試験の内容を説明した。
「要するに、この電話機が良く聞こえるかどうかを試験するんだよ。高い音も低い音も、偏りなく自然に聞こえることが大切なんだ。聞こえすぎても頭が痛くなるし、良く聞こえないと苛々してしまう。一週間前にやった試験はNGだったんだ。それで、設計変更して再チャレンジというわけ」
大崎は試作品の電話機の受話器を装置に取り付ける。試験装置のチャンネルをいじりボタンを押し、印刷された試験結果を手に取っては、顔をしかめたり頷いたりする。
試験が終わった大崎は、データをまとめた。結果を上司の目黒に説明しているあいだ、目黒には二件、大崎には一件電話がかかってきたので、話し合いが終わると二人は、それぞれ折り返し電話をかけた。
大崎は電話を切ると、要求された書類をさっと書き終えファックスして一息つく。午後八時。エンジニア達は当たり前のように働いており、帰り支度をする者はいない。
「もう、食堂は閉まってるな。売店の横にある自販機でカップラーメンを買おう。近田君、それでいい?」
「はい、近田はカップラーメンが大好きです」
大崎がカップ麺を食べていると、製造部の阿部が近くに来る。大崎は麺をすすりながら、「えーと、それはですね」と言いながら、質問に答える。食べ終わると、急ぎ足で戻って、設計書を書き直した。
「電話の設計部は、いつもこんなかんじなんだよ。ご飯を食べそこなうなんて、しょっちゅうある。技術の連中はみんな痩せてるだろう? ここにいたら太れないよ」
「近田が元々いる交換機の設計部も同じです」
近田が寮に帰ったのは、十時半過ぎだった。多摩工場の西門から寮の玄関までは、歩いて一分ほどの距離である。向かい側は女子寮だが、もちろん男性は入ってはいけない。が、窓から侵入して彼女の部屋に泊まった奴がいた、という噂はある。女子寮の門限は十時で、外泊には許可証が必要である。
近田は部屋に着くと、シャワーを浴びるため、急いで一階の風呂場に行く。部屋に戻ると、同室の大久保が仕事から戻っていた。当時、寮は二人部屋だった。
入社して一年目は学生のノリであるが、二年目というのは、会社のあらゆることが見えてくるときでもある。
「大久保さん、おかえりなさい」
「ただいまー」
「ずいぶん疲れてますね」
「あぁ、毎日、朝七時に起きて帰りは十一時。セブンイレブンっていうんだと。先輩が言ってた。おまけにオレの仕事は『一に体力、二に体力、三、四がなくて五に体力』、頭は要らないだとよ」
大久保の足元には綿ぼこりが泳いでいる。
「そういえば、今まで確かめもしませんでしたが、大久保さんはどんな仕事をしているのですか?」
大久保は、近田の敬語にも慣れた。
「衛星通信システムさ。オレ達は、衛星が送ってきたデータを受信する地上局のアンテナを設計してんだ。聞こえはいいけど、入社以来、オレは一度も頭を使っていないんだぜ! 頭を使う仕事がしてーよ!」
「そうだったのですか。近田は夜空の星を眺めるのが好きです。宇宙には夢があります。きっと、人間は死んだら、地球にさよならして、遠くの星で新しく生まれ変わって暮らすような気がしてなりません」
「そうかもしれねーな。もともとオレは宇宙開発事業団に入るのが夢だったんだ。結局、芝通になっちまったけどよ。衛星通信の仕事に配属されたまではよかったけどよぉ、毎日仕事に追われて、土曜日も出勤、これが現実さ」
「だから日曜日になると、大久保さんは石のように寝てらっしゃるのですね」
「おかげで、彼女と会う時間もねーし、電話をしたくても、寮には公衆電話が二台きり。いつも混んでて使えやしねーよ。彼女が電話してきても話中ばかり。芝通は電機メーカーだろ? 構内交換機だって、作ってんだろ? だったら、自分の会社の寮くらい各部屋に電話機つけろってんだ。なぁ?」
「確かに、そのような気もいたしますが、なにぶん近田には彼女というものがいないもので。何も不自由はないのです」
大久保は、「そうか」とうなずく。グラスのアイスコーヒーには青カビが浮いているし、ビールの缶にはタバコの吸殻がもう入らないくらい詰まっている。
「オレ達って、プライベートも、ゆっくりメシを喰う時間も、彼女とセックスする暇も、ないものだらけ。会社には、結婚相手になるような女の子も少ねーしなぁ。まわりをみると、三十歳過ぎても独身が多いだろ? オレも多分そうなるんだろーな。このまま、ここにいてもいいのかって、不安に思うときもあるんだ」
かつて、みどりが芝通を辞めたくなった時に語った言葉は大久保の頭には残っていない。
「大久保さんは、渇いてらっしゃるのですね。しかし、近田の先輩は、入社三年目から責任ある仕事を任されるから面白くなるだろう、って言ってました。今日、近田と一緒に働いた大崎さんも、忙しそうでしたが、生き生きしてました」
「そうかぁ……」
大久保は六畳に布団を敷く。万年床になっていないだけ、寮の中ではマシなほうである。一ヶ月間の海外出張を終えて帰ってきたら、畳にきのこが生えていてびっくり、という人もいた。
大久保は、「悪いけど」と言い電気を消すと、すぐに寝息を立て始めた。
|