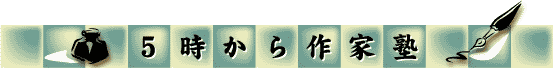| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
4.同期は学生気分のままで
入社した年度によって色がある。偶数年入社は、まじめで優秀な人材が多い。一方、奇数年入社は、個性が強く、にぎやかで遊び好きな人間が多く、理科系らしくないと言われている。あくまでここ――芝通・多摩工場――での話だが。
桐畑と永沢は偶数年入社である。同期には寡黙な人間が多い。みどりが入社したのは1985年、奇数年である。みどりが新人だった頃は、よく集まり、騒いだ。同期だからテンションを抑える必要もないが、飲みに行く時は社章を外せと言われていた。駅前の塀に登って「注目!」と叫ぶ者もいるし、胴上げをする者もいる。もちろん、店から出入り禁止を言い渡された者もいた。
1985年入社は千三百人。そのうち三十名が多摩工場に配属された。女性は六名である。
夏の大型連休まであと一週間、セミの声も耳につく金曜日。会社近くの居酒屋には、あちこちに芝通社員の姿がある。そのなかには85年入社組の姿があった。
山田祐子は席に座ると、
「のど渇いちゃったかも〜」
ビールを一気で飲み干すや、さらに
「祐子ちゃんは、次はねぇ、ワインにしようっと」
と女子大生言葉を連発。アルコールの匂いを嗅ぐと、体が学生時代の合コンを思い出すらしい。祐子が卒業した大学は小平市にあって、東京の私立女子大のなかで真っ先に名前が出てくるような派手さはないが、国際性や先取性のある、知的な女性を社会に輩出している。
祐子は光伝送通信のシステム設計課で働くエンジニアである。時代の先端を行く職場にいる祐子であるが、悩みは古典的。男女差別である。祐子たちは学生と変わりない話題で盛り上がったが、赤ワインのボトルが空になる頃、村上が、「最近残業が多くて……」とぼやくと、祐子は箸を止めて睨む。
「いいよねっ、男は!」
しまった、と村上は愛想笑いをするが、もう遅い。
「私たち女性社員には残業規制があるのよ! 一日に二時間を超える残業をしちゃぁいけないし、一ヶ月の残業時間は二十時間までなの。だから私たちには、残業規制の範囲でできる仕事しか回ってこないのよ。もっと仕事をしたいのに、できないのよ!」
規制を無視し、夜間に査察が入ると女性が机の下に隠れるようなことをしていた会社もあったが、芝通は組合も強いし、「法だけは守る」という姿勢を貫いている。
「男女雇用機会均等法のおかげで、再来年には、うちの会社も女性の残業規制、なくすらしいぜ」
と大久保が言うが、祐子は返事もせずワインをあおり、
「女性社員は部長になれないなんて言わせないぞぉ! 男女差別と戦ってやるぅーッ!」
とカラんで、またワイングラスが空になるのであった。
まだ飲み足らない何人かは、いつも通り、村上のアパートに行くことになった。そのなかには、祐子はもちろん、みどりの姿もあった。
「祐子ちゃん、これ好きなの」
祐子は部屋に上がると、村上が買ったばかりのバランタイン17年を見つけ、抱え込みロックで飲む。ボトルが空に近づいた時、祐子は足元をふらつかせ立ち上がる。
「祐子ちゃん、おしっこしたいの」
ファンデーションは剥げ、口紅も落ちているのだが、赤いリップライナーだけは縁に残り、唇を形取っていた。祐子は二、三歩進むと、クローゼットのドアを開ける。
「ここトイレ?」
と言いながら、パンツに手を当て中腰。トイレではないことを指摘されると、
「アー、間違えちゃった」
と口走ってガハガハ笑い、次々と部屋中のドアをあけまくる。トイレに辿り着けない祐子は、次第に切羽詰まってくる。終いには、「トイレどこー?」と叫び、見かねた村上に連れられ用を足したのであった。泥酔した祐子はこのことを全く覚えていないのだが、この事件は、後々まで同期の間で語り継がれることになる――数あるなかの、ほんのひとつとして。
ちなみに、村上は港区にある大学を卒業している。そう、どんなに不細工な男性でも大学の名前を言っただけで女の子にモテてしまう、あの大学。理科系のキャンパスは四年間とも日吉であるが、村上は女性の扱いには慣れているし、白シャツ一枚にもこだわりをもって買うのである。
大久保はというと、新宿区にある私立大学、「ミヤコノセイホク……」を卒業している。服装はTシャツにジーンズ。みどりに焼酎のお湯割がおいしいことを教えたのは大久保である。さらに、得意技といえば麻雀の点棒計算。おそろしく速い。
当時の芝通では、どこの大学を出たかということも出世に影響した。歴代社長は、桐畑と同じ大学を卒業した人が多い。必ずしも、大学の難易度ランキング順に出世するわけではないが、事業部長以上の職についている人は、その大学を出ている人が一番多い。それに続いて多いのは、東京都内有名私立、上位二大学、村上と大久保の母校である。
「じゃあ、桐畑さんって、いつかは社長になるのかな?」
みどりがそう言うと、大久保がみどりの顔の前に人差し指を立てて、チッチッとふる。
「社長は法学部とか経済学部出身の人間ばかりだってこと知らねーの? 芝通の歴代社長で理科系出身は数えるほどさ。確か、電気工学科はいたけど、機械工学出身で社長になった人はたぶんゼロだな」
「そうなんだぁ。知らなかった……。どっちみち、芝通にいたら、私は出世に縁遠い人なのね」
みどりの母校は東京ドームの近くにあり、本部は八王子で、法学部が有名である。もちろん、みどりは社長になろうと思って芝通を選んだわけではない。
「でも、出世しないことを突きつけられると、芝通にいる意味がわからなくなるの。私、会社の選択、誤ったかな?」
大久保は、メガネの奥にある二重の瞳を大きく見開く。なにかあったのか? という顔だ。みどりは、本気で会社を辞めたいと思っていることを告げる。どちらかというと愚痴に近い話を、大久保は相づちを打ちながら耳を傾けた。
「やめるのはどうかな。人間なんて、どこに行っても不満はあるじゃん。パラダイスを探し求めたって、ホントのところ、そんなモン、存在するはずねーよな。なら、今いるところでどうすっか、知恵を絞ったほうがいんじゃねーのか?」
大久保はみどりの瞳をのぞきこむ。
「そうなのかな……。それとね、上司の桐畑さんのことなんだけど……。頭が良いのはわかるけど、言葉が足りない分、つかみどころがないのよ。会話もちぐはぐになっちゃうの。いいのかなぁ」
「よくある話だな。桐畑さんのことは気にするこたぁねーよ。信頼したほうがいいぜ。だいたい、うちの課の主任も、オレの上司も、そんな感じなんだ。痩せていて、背が高くて、滅多に笑わないだろ?」
みどりは、ウンウンとうなずく。
「もしかして、大久保君の上司たちって、桐畑さんと同じ大学なの?」
「あぁ。寡黙な遇数年入社。おまけに修士」
「あの大学の大学院を出ているの!?」
「そうさ。でも、考えようでは楽だぜ。深く付き合わなくていいし。ゴマすりもなし。課の飲み会以外なら、オレたちって気が合った奴としか飲みに行かないじゃん?」
「そうだねぇ」
「オレの友達で、営業やってる奴がいるけど、毎日、飲みに行くらしい。文系なんだけど。景気がいいから、手当ても多いだろ。現金を持って、夜十時から飲みにいくって言ってた。このあいだそいつに会ったんだけど、寝てないせいか、昼間からハイなんだぜ。やけに熱いし……。そういうのも悪くないけど、毎日となるとオレはどーかな……。オレはクールな上司のほうが合ってる気がする」
「二十四時間ハイテンションな上司と、笑わない上司。どちらがいいか、究極の選択ね。そう考えると、私は桐畑さんが上司でよかったのかもね」
大久保が言うには、芝通には桐畑タイプが多いらしい。ということは、ここにいる村上と大久保もいずれ、桐畑みたいに仕事に染まっていくのだろうか?
「学生サークルじゃないんだし、社会人らしくならなきゃいけないのはわかってる。でも、同期と飲むときは、このまま変わりたくねーな」
そんなわけで、いつまでたっても学生気分が抜けない85年入社組。同期が多いのも、良し悪しである。
|