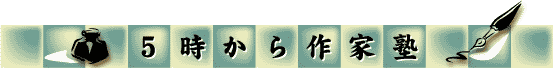| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
12.セクハラはどうやら本当にあったらしい
セクハラという言葉が世間で広く使われるようになったのは、1989年頃のことだった。アメリカでは、1980年代から訴訟が相次ぎ、日本でも1989年、福岡地裁で初の提訴があった。セクハラ対策が徹底される前の時代には、今なら即刻クビになるようなことも、堂々と行われていたようである。ということで、今回は、セクハラは本当にあった? というお話し。
*
新橋美香は、ポケットベル管理課で事務をしていた。目鼻立ちがはっきりとして、今時のアイドルで言えば松浦亜弥に似ている。配属面接では、受付嬢を勧められたが、希望通り事務職についた。入社五年目の二十三歳。同じ部の先輩と三年越しの恋を実らせ、もうすぐ寿退社する予定である。
「最後に打ち合わせをしておきたいことがあるので」
部長の中村は、会議室で美香を待つ。関西のおぼっちゃま大学を卒業し、順調に出世してきた。そのうえ、ネクタイのセンスといい、ロマンスグレーの髪といい、素適で清潔。女子社員の憧れの的でもあった。
「やぁ、新橋さんが辞めてしまうのは残念だけど、めでたいことだからやむをえないね。今週、二人でお祝いの席を持ちたいのだけど……」
尊敬する中村からのお誘い。
「新橋さんは、今までよくやってくれたし。お礼も兼ねてね」
美香は即座にOKした。
待ち合わせた喫茶店は、クラシックが流れ、ブレンドが一杯千円もする珈琲専門店。芝通の従業員は来そうもない場所だ。
そして食事に入ったレストランは、さらに高級なフランス料理店。美香の部署でこの店が似合うのは、中村くらいだろう。ワイン選びもスムーズで、ナイフやフォークの使い方も堂に入っていた。
「結婚式は来年の六月だったね」
中村は結婚相手の藤沢の上司でもある。
「彼もよくやっているねぇ」
「ありがとうございます。今後とも、よろしくお願いします」
美香は深々と頭を下げる。
「藤沢君なんだけど、次の評定はAランクで出そうかと思っているんだよ」
毎年、年度末になると、上司は部下一人ひとりについて評価をすることになっており、その結果は来年度の昇給に影響する。出世は部課長の評定にかかっているのだ。「中村部長って本当にいい人!」と美香は思った。
「ごちそうさまでした」
「どういたしまして」
せっかくだからと、中村はジャズが流れる店に美香を連れて行く。ピアノが会話のじゃまにならない音量で響き、ほどよい間接照明が天井を照らしている。美香はカクテルを飲みながら芝通での思い出話しを語った。送別会で大泣きした先輩のこと、社内旅行に行ったときのこと、「楽しかったですよね」と美香はカクテルに置いた視線を中村に移す。すると、じっと美香を見つめている中村が目に入る。美香は、はぐらかすように話を続けるが、中村は上の空。さっきまでとは違い、視線が男の目になっている。
<まずい!>
美香はとっさにそう思った。中村は、誰が見ても素適な男性だが、奥さんもいるわけだし。なにより、美香は半年後に藤沢と結婚するのだ。
<やっぱり、この人とセックスするなんて、絶対イヤ!>
ならば、ここはさっさと退散するしかない。
「もう、遅いからそろそろ帰らないと」
そんなことで、中村は引き下がらない。
「そう言わないで、もう少しどうかな」
「いや、今なら終バス、間に合いますし」
「タクシーで送るから大丈夫。チケットを使いなさい」
中村は、部長以上の役職者に支給される接待用のタクシーチケットをちらつかせる。
「ところで、これからも月に一回くらいどうかな」
美香はすぐにでも席を立ちたい気持を必死にこらえ、うつむく。
「藤沢君の仕事の相談にも乗るから……。いいだろ?」
ここで断ったら、藤沢の評定は下げられるのだろう。自分のせいで、夫が努力しても出世できないなんて哀しすぎる。やっぱり、断れない。美香は仕方なく頷いた。
*
釜田ともみは、気になることがあった。
「一週間くらい前から、家の留守番電話に変な声が入っているのよ」
彼女は、桜井の同期である。
「どんな声?」
桜井は身を乗り出す。
「あぁぁ〜みたいな、低くて地味でいやらしい声」
ともみが答えると、同性愛系の桜井はにやける。
「うらやましいわ。うちにも来ないかしら」
「うらやましくないわよ。相手がはっきりしないから気持ち悪いの。うちの留守番電話って、同期の武田君が設計した機種で、実用試験の名目でもらったのよ。それがさぁ、試作品のせいもあって性能が悪くて。喋っている声とは違うから、わかりづらいし」
「だったら、手当たり次第、一人ずついやらしい声を聞くようなことをすれば、誰が犯人かわかるんじゃない? なんだったら、この桜井がともみさんに代わって……」
「そうじゃなくて……」
桜井はともみの顔を覗き込む。
「なんか怪しい。本当は、もっと重大なこと、隠してるでしょ」
「わかる? 実はさぁ……」
先月のある土曜日、ともみは休日出勤をした。月に二回は土曜日も働くので、珍しいことではない。が、その日は特別。朝一からの打ち合わせで、他課の人間と白熱した議論が続き、仕事が終わると、ともみは疲れで溜息をついた。課長の田中は打ち合わせがうまくいったので機嫌がいい。
「釜田さん、よくやった。疲れただろう。車で送ってあげるよ」
芝通の多摩工場で、自動車通勤者は珍しくない。駅から離れたところにあるし、都心に比べたら渋滞がましだからだ。信号待ちに差し掛かったときに、田中はハンドルを握りながら、ともみに話しかける。
「おなかすいたね。ご馳走するから……」
「でも、課長は……、奥様が手料理を作ってお待ちなのでは?」
「いつもはそうだけど、『今日は打ち合わせが何時に終わるかはっきりしないから、食事はいらない』と言って出てきたんだ。家に帰っても喰うものがない」
「では、お言葉に甘えて」
「西湖にいい店があるから、そこに行こう」
多摩工場は、中央高速道路の八王子インターまで、車で十分ほどのところにある。富士五湖まではそう遠くはないのだ。ともみは会社の帰りに、同期でドライブがてら食事に行くことも何度かあった。
車は走り出す。しばらくすると、――ホテルのネオンがチラホラ。ともみは、「ちょっと待って!」と思ったが、「これは近道なのかも?」と思い、黙ったまま。すると、車は左にウインカーを出し、ピラピラカーテンをくぐってしまうではないか。
「今日は、ハードだったから、だいぶ疲れているようだね。まずは少し休んでからにしよう」
「私、疲れてませんよ。元気ですよ、ほら」
ラジオ体操のように、ともみは両手を上げ下げする。
「いや、君は疲れている。ちょっと休むだけだよ。なにもしないから安心して」
<そんな女子高生を口説くような言葉を使うな、っつーの!>
「いーえ。疲れてませんてばッ!」
と、噛み付くのが精一杯である。すると田中は、
「お互い、大人なんだから……」
と、かなり強引。
断わったら気まずくなるだろうし、それを振り払いながら普通の顔を作って仕事をするのも面倒臭いし、これから先、雑用しかやらせてもらえなかったら哀しすぎる、などと考えているうちにともみは面倒臭くなり、「まっ、いっか」と田中の後をついていった。
「それからしばらくして、また『送るよ』って言ってきたのよ。さすがに『タクシー呼んでますからけっこうです』って断っちゃったの。そしたら、いやらしい留守録が始まったのよね。田中課長の声かどうかはっきりしないけど」
「でも、似てるのね?」
ともみは桜井から目を逸らし、うつむいたまま頷く。
「芝通って、変わってる人が多いからねぇ。気をつけなさい」
これ以降も、忘れかけた頃に留守番電話に声が入るという。
*
「芝通は、変わっている人が多い? 一番変わっているのは、桜井さんじゃないですかぁ」
みどりは大口を開けて笑った。桜井のアパートで飲んでいる。桜井は、芝通の社員情報に詳しい。どうしてそんなことまで知っているのか、と思うほどいろいろなことをよく知っているのだ。
「ところで、小林さんは、セクハラされたことないの? 鈴木主任って、飲むと隣りに座ってる女の子のお尻触るって聞いたけど」
「ない。何度も、隣りに座ったことあるけど、一度も触られたことはない」
「じゃぁ、飲み会の後とかに、ホテルに誘われるとか、そういうことは?」
「スカートのまま胴上げされたことはあるけど、ホテルに誘われたことはない」
「普通、女の子は胴上げされないのにね。やっぱり、あんたは男として扱われてんのね。かわいそー」
「でも……」
機械設計課の送別会の日。みどりは、桐畑のことが気になっていた。一次会で帰ろうと、寮の方へ向かう桐畑を追いかける。
「あのぉー、せっかくだから飲みにいきませんか」
「最後だから、いきますか」
みどりはアッサリ断られると思っていたので、却って戸惑ったが、近くの静かな店に入ることにした。桐畑と飲みに行くのは、初めてである。食事すらしたことがなかったのだ。
みどりは緊張して、何を飲んだのかも覚えていない。ただ、桐畑は、よく喋った。普段は、標準語を話すのだが、その時は関西弁だった。みどりは関東で暮らしていたので、それが大阪か神戸か京都かさえもわからない。みどりは、桐畑の言葉に耳を傾けた。
本が好きだということ。彼の実家は自営業で、両親は厳しかったこと。幼い頃、兄か姉が欲しかったこと。
みどりは、桐畑の話に引き込まれていく。興味あるものが未知な部分を持っていると、みどりはどうしてもそれを知りたくなるのを抑えられない性格である。
「それから?」
みどりが訊くと、桐畑は、開発の仕事が好きなこと、人から「あーしろ」、「こーするな」と、干渉されるのは大嫌いだということを話す。冗談を交えて話す桐畑は別人のようだった。
<もっと、もっと、知りたい>
みどりは、桐畑の全てを知りたいという気持を我慢することができなくなっていた。
「あのぉー、桐畑さん。私とセックスしませんか?」
桐畑は、ポカーンとした顔で、
「小林さんは、変ってる」
と標準語で言い、また話の続きを始めた。
そこまで、みどりが話すと、桜井は大声を出して笑う。
「桐畑さんも困っちゃったんじゃない? 小林さんがしたことって、逆セクハラよね? 女が男にするセクハラ。」
「そうかなぁ。だって、その時はそう思っちゃったんだもん、しょうがないじゃない」
みどりは、目の前にあるウイスキーを飲み干した。
「セクハラって言ったのは冗談。桐畑さんは小林さんの元上司だから、正確に言うとセクハラにはならないわ」
「……そうだとしても、なんか私って悲しい。どうしてモテないんだろ?」
「まぁまぁ。そのうちいいことあるんじゃない」
桜井の言葉は慰めになっていない。男性のようなみどりと、女性のような桜井。奇妙な二人は、朝まで飲み続け、空が紫色になる頃、眠りについたのであった。もちろん、別々の布団で。
芝通の男性で、みどりを女性として扱ってくれるのは、桜井だけかもしれない。
|