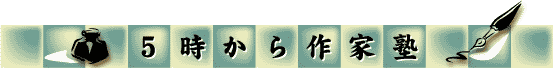| 第1章 こんな私たちでありますが |
|
――バブル編 '85〜'89
|
1.理科系な社会
世の男性には、文科系な男性と理科系な男性がいる。話しがうまく女の子を喜ばせるのが得意なのは、文科系な男性に多い。一方、理科系な男性はというと、口下手で気がきかないけれど、付き合ってみると誠実で優しかったりする。もちろん、なかには例外もある。
それはともかく、理科系な人間が集中している場所といえば、大学の理工学部の研究室、企業の情報システム部、ハイテク企業の研究・開発・設計部門……、といろいろある。
例えば、ある電機メーカーの研究開発部門。職場には、一流大学理工系卒の人間がひしめく。彼らの多くは、なぜか近視である。そして、同じ理科系な人間に囲まれて生活しているせいか、自分の置かれている環境が、特殊な世界だということに無自覚でもある。時おり、全世界の人間が自分と同じ理科系な思考回路を持っていると勘違いしている人もみられる。
読んでみて、「ああ、こういう人、私のまわりにもいる」と思うか、「世の中には、こういう人もいるんだ」と感じるかはわからない。ただ、どちらにしても、ちょっと変っているが、憎めない電機メーカーの人間たちの話から始めようと思う。
*
1985年、バブル景気が始まる前のこと。電機メーカー「芝通」に入社したばかりの小林みどりは二十二歳。二ヶ月間の研修が終わって、渡された配属先は、ファクシミリの機械設計課だった。芝通は半導体、情報通信、OA機器を主力に置くハイテク企業で、みどりのような理科系卒は、研究所か、工場内の開発・設計部門に配属される。そこは機械工学系の男性だけの職場で、女性が配属されるのは機械設計課が始まって以来のことである。実のところ、みどりはファクシミリなんて触ったこともない。それなのに設計なんてできるのだろうか?
「小林みどりといいます。よろしくお願いしま〜す」
配属になったばかりのみどりは、上司の桐畑に深々と頭を下げたあと、合コンで本命に見せるような最高級の微笑みを向けた。桐畑は背が高くメタルフレームのメガネが知的。みどりが期待した以上の風貌だった。狭くて赤い門で有名な、あの大学を卒業している、入社八年目のベテランらしい。
しかし――。桐畑は、最低限の挨拶を返すどころか、眉ひとつ動かさない。
「ここが小林さんの席です」
そっけない返答にもめげずに、みどりは笑顔を保って、「ハイッ」と答える。桐畑は事務的に設備の説明をし、
「私は会議がありますので……」
とだけ言って、みどりの前を通りすぎて行った。
とかく新入社員というのは不安だらけで、上司と良い関係を築いてうまくやっていきたいと思うものである。しかし、桐畑は間違いなく、みどりの不安を掻き立てたのであった。
二日が過ぎたが、相変わらず桐畑は簡潔であった。
「あのぉー、きょうの……」
緊張で固まっているみどり。遮るように桐畑は答える。
「開発会議ですね。三時からです」
確かに、みどりの訊きたいことは単純である。みどりが、「あのぉー、きょうの……」と言っただけで、何を答えたらいいのかわかってしまうらしい。群を抜いて頭の回転が速い。課長の日野と話すときは、最後まで聞いてから答えるのだが、きっと失敗の許されない技術的な話だからだろう。
「次機種は、新規に開発する部分がたくさんあるから、大変そうですねぇ」
懸命に笑顔を作るみどりに桐畑が返した言葉は――。
「大変って言われても……」
大学のサークルじゃないんだから厳しいのは当たり前です、と言いたそうである。二人の対話は、ちぐはぐになり、みどりの不安はますます大きくなる。
ところで、機械設計課でも新人歓迎会は毎年行われる。今年は、近くの中華料理店。歓迎会なのに、「静寂」。一気飲みをする人も大声を出す人もいない。みどりは隣りに座った先輩の桜井と話をするものの、すぐに話題も尽きて、黙々と料理を食べるしかない。
<だれか盛り上げてくれないのかぁ〜>
と桐畑に視線を送ると、桐畑はやや赤い顔で、部長と課長の日野とを相手に仕事の話をしていた。
「私はカッターにあの素材を使うことには……」
桐畑は、テーブルにある紙ナプキンを使って、図まで描いて説明している。酔っているはずなのだが、頭は働いているらしい。
大学時代のテニスサークルでの飲み会とは、あまりにも格差があり、みどりは唖然とするばかりであった。
それはともかく――、二次会は、近くのカラオケに行くことになる。
「桐畑さん、帰っちゃうんですか? 二次会、行きましょうよ」
酔いも手伝って、みどりは大胆。桐畑曰く。
「私はこれで帰ります。部屋で、読みかけのモームを最後まで読みたいので」
いつもより言葉は長い。が、みどりの誘いには乗らない――あくまで隙のない男。
「モーム? 作家ですか?」
「『月と六ペンス』が有名ですが、今私が読んでいるのは『人間の絆』です」
「本を読むのが好きなんですね。私は、滅多に本は読まないのですが、村上龍は好きです」
「私は、現役作家の作品は読みません。時を越えて生き残ったものだけ読みたいのです」
「もしかして、音楽もクラシックしか聴かないとか? 桐畑さん、小林幸子、知ってます?」
「小林幸子? 知りません。部屋では、ドビュッシーかラヴェルを聴いています。時折シューマンを聴きますが、やはり心に響きます」
桐畑は、「それでは」と言い、寮の方向へ歩いていく。鞄はほころび、肩紐は切れそうになっていた。
二次会は打って変ってにぎやかだった。一次会では、部長もいて皆緊張していたらしい。
「どうして桐畑さんて、ああなの?」
みどりは、二年先輩の桜井に聞く。彼も桐畑の部下である。
「会社にいるときの桐畑さんは、ファクシミリを開発することしか頭にないの」
桜井は、少しだけ首を傾けて話す。みどりは、機械設計課に同性愛系の人がいると聞いたことがある。まさか、「それって桜井さんですか?」とは訊けない。しかし、周りを見渡すと桜井以外にそれっぽい人はいない。
「小林さん。桐畑さんにとって最重要なのは、効率よく仕事をして成果をあげること。部下になったばかりの小林さんといい人間関係を築くことは、残念ながら優先順位が低いの。でもねぇ、芝通のファクシミリは、他社がやってない新しい技術をたくさん開発してきたの。その半分くらいは、桐畑さんが任されたところなのよ。桐畑さんがいなかったら、ここまでは来れなかったわ。ねぇー」
桜井は、隣りの席に座っている同僚に同意を求める。
「桐畑さんは、ちょっと変わっているけどすごいのよ。だから小林さんは、桐畑さんに普通の人の考えを押し付けないほうがいい。桐畑さんが、普通の人になっちゃったら、きっと今みたいなすごい設計はできなくなるような気がするもん」
桐畑はプライベートでもクールなのだろうか。けっこう、親父ギャグを連発して、彼女から白い眼で見られているかもしれない。また、桐畑のようなタイプが結婚すると、奥さんには
「あー、パパったら、また洗面所を水浸しにしちゃって。あーッ、引出しは開けたら、閉めるッ!」
などと小言をいわれている人も多い。桐畑はまだ独身であるが、家庭をもったら、そういう感じになるのかもしれない。
桐畑は、あと三年で入社十年。同期の中でもいち早く主任になるだろうといわれていた。
ちょっと変わっている上司に、同性愛系の先輩。みどりは頭を抱えた。
話は変わるが、ハイテク企業は研究開発情報の漏洩に神経質である。芝通では、開発中の製品は暗号名――例えば「Z30」といったコードネーム――で呼ぶのが決まりになっている。電車、バスの中で、開発中の製品を話題にすることは厳禁、会社の外に出たなら課の人数すら口にしてはいけないのだ。工場へ入る時には、門衛に従業員IDカードを見せる。研究開発部門の建物は従業員IDカードをリーダーに通さないとドアが開かない。これは他社も同じである。芝通が他社の開発情報を盗もうと思っても、簡単にはできないし、設計部に他社の情報が入ってくることもない。もちろん他社の製品を手に入れて、技術を盗もうなんてこともしなかった。
ところが――。ある日、みどりが実験室に入ると、桐畑が棚の前で腕組みをして立っているのが目に入った。棚にはファクシミリがずらりと並べられている。電源も入るし、送受信もできる。過去に芝通が開発したものだ。みどりは、ファクシミリの数が増えていることに気付く。昨日はなかったはずの他社製品がいつの間にか並んでいる。なぜここに他社製品があるのだろうか? まさか、他社の技術を真似ようとしているのだろうか。みどりが、「あのぉー」と声をかけると、桐畑が振り向いた。
「我々は、他社製品を買い込んで調べるなんて真似はしませんよ」
指でメガネの縁を持ち上げる。桐畑の説明では、他社が売り出した製品を調べて技術を真似しても意味がない、ということだ。特許に引っかかるか、そもそも製品化する頃には、その技術は既に古いものとして価値が落ちている。
「では、なぜ他社製品がここにあるのですか? いったい何のために?」
「わからん」
みどりは初めて桐畑の口から、「わからない」という言葉を聞いた。
人間である以上、一流大学を卒業していても、できないことはたくさんある。桐畑が苦手なことといえば、仕事以外のことに気を配ることだろう。では、みどりのできないことはというと――。他社製品を購入した理由は、この理科系な人間の弱点にあった。
|